2022年4月から、学校で金融教育が導入されます。様々な背景から今後必要な教育の一つと判断された上での導入ですが、日本では前例がないため、どのような教育になるのかわからないといった声もあがっています。
そこで本記事では、金融教育を導入することになった背景や金融教育の授業内容、今後の課題などについて見ていきます。
- 金融教育が導入されることになった背景
- 金融教育の授業内容
- これからの課題として考えられること
目次
金融教育が導入される3つの背景

日本は海外に比べて金融教育が遅れているといわれていますが、2022年4月から義務教育として導入されるようになった背景は主に3つあります。
少子高齢化による公的年金の減少
日本は少子高齢化により、年金保険料の収入が年々減少している一方で、高齢者が増加して公的年金制度の財政状況が悪化しています。
この状況は今後も続くと予測されており、老後資金として自分でも資産形成をする必要性が高まってきました。しかし、資産形成はリスクを伴うため、リターンとのバランスを取りつつ運用するための知識を身につけることが急務です。
そこで、iDeCoやNISAなどの制度面だけでなく、利用者の資産形成スキルを高めるために金融教育の導入が決定されました。
欧米などの先進国に比べて金融教育が遅れている
日本は個人資産を現金や預貯金として保管している割合が高く、リスクを伴う投資には消極的です。
一方、欧米などの先進国では資産形成を当たり前に行っており、個人資産の約半分を債券や投資信託、株式などの金融商品に充てています。
預金ならば損をしないという意見もありますが、実際にはインフレのリスクがあり、長期的に運用せずに保管しておくことは得策とは言えません。
このような金融に関する知識の遅れを少しでも取り戻すべく、金融教育の義務化が進められています。
成人年齢の引き下げで懸念されるお金のトラブルの増加
金融教育の義務化と同時に、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられます。
日本では18歳と言えばまだ学生で社会経験が不足している人も多いですが、成人となった以上はクレジットカードの作成や決済、銀行口座の開設、借入れなどの様々な契約を自分の責任で行わなければなりません。
そのため、詐欺などの被害に遭ったときの損害が未成年の時よりも拡大すると懸念されており、金融教育の必要性が高まっています。
生きる力を養うための金融教育の授業内容とは
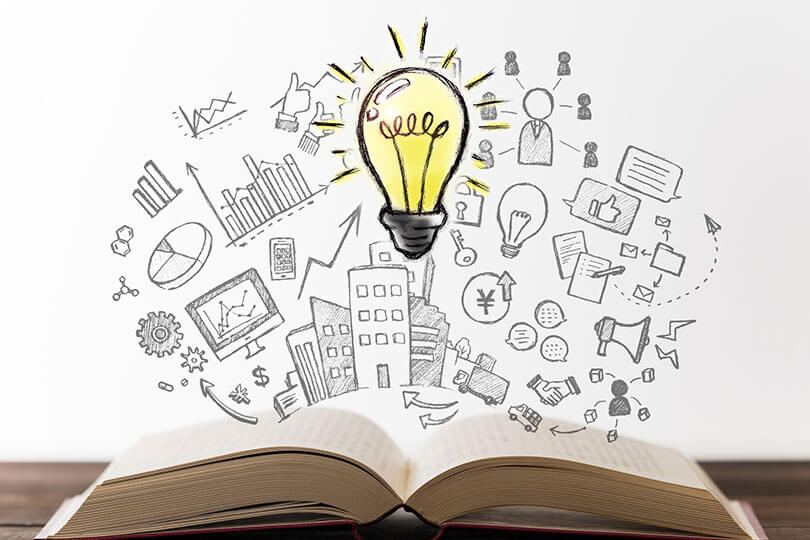
金融教育の必然性が高まっている状況で、金融庁は高校生の金融教育の目標を次のように記載しています。
暮らしを通じてお金のさまざまな働きについて理解する
まず、個人の生活においてどのようにお金が動いているのかを理解していくために、家計について学んでいきます。家計管理の基本に始まり、給与明細の見方や家計簿の収支バランス、借入れ等に関するリスク管理を理解することで、リアルタイムに家計の現状を把握することが可能です。
また、人生において結婚や妊娠出産、家の購入、転職、子供の進学など様々なライフイベントが発生しますが、これらについてあらかじめある程度の予測を立てて生活設計をしていかなければなりません。
そこで、教育資金や住宅の購入、老後資金などの大きな出費について確認するとともに、事故や病気、失業、不景気などのリスクに備えた家計管理ができるようになるスキルも学びます。
生涯を見通して進路や職業を決め、生活設計に基づいた家計シミュレーションやローンを組めるように、フィナンシャルプランナーに近い知識やスキルを身につけます。
預金や貸出を含む、銀行の基本的機能について理解する
一方で、資産形成には金融商品の基本やリスクとリターンの関係を理解していなければなりません。
そこで、具体的に銀行の基本的機能として預貯金や貸出などについて学ぶとともに、民間保険や投資のための株式、債券、投資信託などの商品についても学習します。
これにより、資金の流れや運用におけるリスクとリターン、金融商品の選び方などの知識とスキルが身につきます。
金融教育のカギとなる今後の課題

金融教育は日本では始まったばかりということもあり、今後にいくつかの課題を残しています。
教員のマネーリテラシー向上
金融教育は家庭科で実施されますが、これまでの教育内容は調理や裁縫などが中心で、教員自体が金融教育を受けたことがありません。
そのため、今後金融教育をする上でまず教員の教育が優先されるべきであり、金融教育に関する専門的かつ集中的な研修などの対策が急がれます。
デジタル教材の活用
金融教育ではリアルタイムに変動する社会に適応しやすいデジタル教材を活用する予定ですが、その活用方法についても適切な指導が必要です。
ツールの使い方だけでなく、デジタルデータの見方や分析方法、応用などについての指導も今後の課題の一つと言えるでしょう。
生活の向上に役立つ金融教育
このように、金融教育の導入は若い世代の金融リテラシーを育て、個人の生活スキルを高めるために有効な政策といえます。
個々の金融に関する判断力や知識が向上することにより、企業の成長や経済の活性化も期待できるでしょう。学生にとっても生涯役に立つ知識ですので、日常的に様々な情報に興味を持ってほしいところです。

