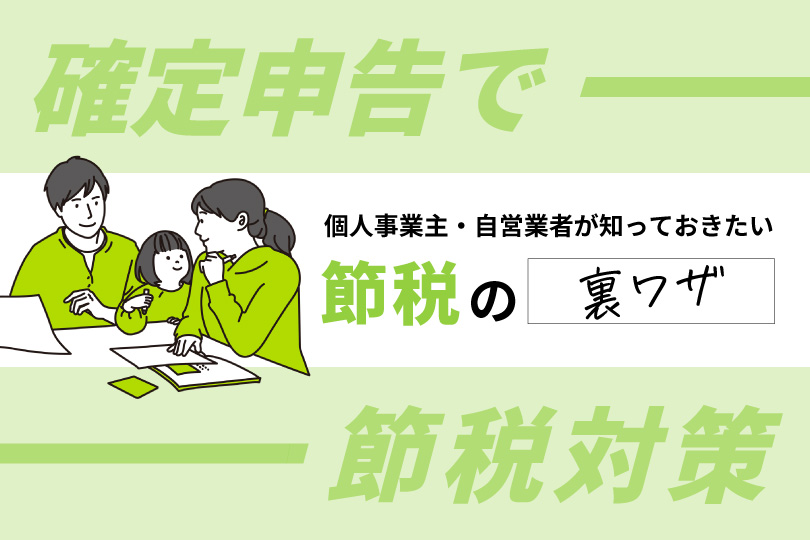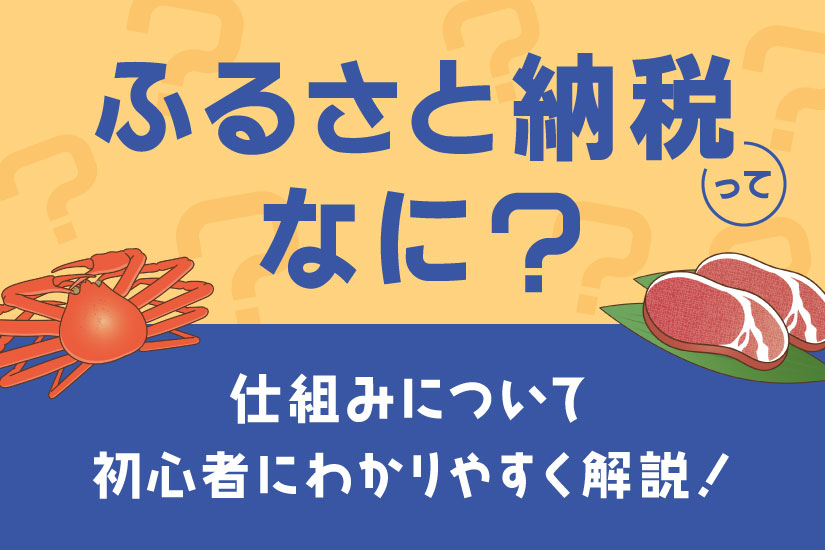昨年の所得が多かったために所得税・住民税が増えてしまい支払いが大変だった。
けれども今以上の節税の方法が見つからない、経費を使う以外の節税方法が知りたい!と悩んでいませんか?
この記事では、自営業者である個人事業主・フリーランスが実践したい節税のコツをお伝えします。
今年は同じ失敗をしたくない、税額を減らしたいという方にぜひ最後まで読んでいただけると幸いです。
- 自営業者が確認すべき3つの節税ポイント
- 覚えておきたい4つの節税の裏ワザ
- 実践したい節税のテクニック
目次
税金が大きな額となる3つの理由

フリーランス・個人事業主の税金が大きな額となる考えられる理由は主に3つあります。
- 控除を使い切れていない
- 収支を把握していない
- 納めた年金を把握していない
控除を使い切れていない
所得控除とは税金を計算するときに所得から差し引くことができるもので、所得控除の金額が多ければ多いほど納める税額は少なくなります。
所得控除は全部で15種類あります。
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 寄附金控除
- 雑損控除
- 医療費控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
じつは対象になるけれど、制度を理解していないがために使えていない控除があるかもしれません。
収支を把握していない
レシートは一年分まとめて、年末か確定申告の時に一気に処理する!という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかしこれでは節税のチャンスを逃すことになってしまいます。なぜなら年末にできる節税方法は限られているからです。
もし取りこぼしなく節税したいと思うなら、こまめな経費精算を心掛けた方がよいでしょう。
納めた年金を把握していない
自分が今まで何ヶ月分の年金を支払ったか、確認したことはありますか?
年金の未納分を追納すると、その金額がその年の社会保険料控除となって税金の軽減につながります。
もし学生のときに年金を支払っていなかった、免除を受けていた時期がある、という方は節税のチャンスが眠っているかもしれません。
詳しくは「節税につなげる3つのテクニック」で説明します。
4つの控除で節税する裏ワザ

まず確定申告をする前に、基本的な4つの控除をきちんと使えているかどうかを確認しましょう。
青色申告特別控除
現在確定申告を白色申告で行っている方は、ぜひ青色申告に切り替えましょう。
青色申告を利用することで、複式簿記の場合は55万円、簡易簿記の場合は10万円が控除されるという特典を得ることができます。一方白色申告には特別控除はありません。
さらにe-Taxというオンラインによる青色申告(複式簿記)を利用すると、青色申告特別控除の額は65万円になります。
紙で提出する場合と比べると10万円控除額が増えますので、こちらも考慮してみてはいかがでしょうか。
参考:国税庁ホームページ|No.2072 青色申告特別控除
社会保険料控除
国民年金や国民健康保険の保険料は、支払った額が社会保険料控除になります。
もしご家族の分を支払っているのであれば、その分も控除対象となります。
会社員の場合は年末調整で申請しますが、フリーランス・個人事業主の場合は確定申告の際に自分で申告しなければなりません。
確定申告時に必要となりますので、支払ったあとの納付書は必ず保管しておきましょう。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除の特徴は、掛金の全額が所得控除になるということです。
この控除の対象は主に以下の2つです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
個人事業主はiDeCoに月6万8,000円まで拠出することができ、その全額が所得控除となります。
積み立てた年金資産は原則60歳まで引き出すことができない点に注意が必要です。
参考:イデコ公式サイト
小規模企業共済
小規模企業共済は小規模企業の経営者や会社の役員が自分で積み立てる退職金で、掛金の上限は月7万円です。
60歳まで引き出せないiDeCoと違い、退職・廃業時に共済金を受け取ることができます。
しかし加入後20年未満で任意に解約すると、受け取れる金額は掛金総額よりも少なくなりますので注意しましょう。
寄附金控除
寄附金控除を利用する一番メジャーな方法は、ふるさと納税です。
ふるさと納税とは、任意の自治体に寄附をして所定の手続きを行うことで、寄附金のうち自己負担額の2,000円を除いた金額が所得税と住民税から控除される制度です。
ふるさと納税のメリットの一つは、少額から購入できることです。返礼品は、安いものであれば数千円から購入できます。
購入した金額が寄付金控除となるため、節税においても細かい金額を調整する際に利用できるのです。
年間の収支がおおよそ把握できたら、ふるさと納税を利用してみましょう。
ただしふるさと納税には控除上限額があり、自営業の場合は住民税所得割額の2割程度となりますので住民税決定通知書で確認しておきましょう。
節税につなげる3つのテクニック

これまで見てきたように、節税の基本は所得控除などの制度を正しく使うことです。
そうは言われても、いくら使っていいのかわからないし、実行に移すのがめんどくさい!と思われるかもしれません。
そう思ってしまう原因は、今現在、ご自身の年間収支の具体的な金額が把握できていないことにあります。
次に、年間収支の管理方法などを含めた節税につなげるコツを3つご紹介します。
事業用口座を作る
事業に関わるお金はプライベートと分け、売り上げと経費支出のみが記帳される事業専用口座を使いましょう。
そうすることで常に残高を把握することができ、毎月いくら利益が出ているのかがわかります。
もし、昨年よりも収入が増えたにもかかわらず経費の額が変わっていなければ、当然課税額も増えることになります。
専用口座内で毎月のキャッシュフローを把握するのは、節税への第一歩です。
毎月末に帳簿をつける
毎月の収支を把握することで、年末の課税所得を予想することができます。
昨年よりも売上が多いかな?と思ったらふるさと納税をするなど、臨機応変に対応できますね。
ついレシートを溜めてしまう、経費の計算を後回しにしてしまう方は、取引の自動化ができるクラウド会計ソフトを使ってみてはいかがでしょうか。
年末になって焦ってしまうことのないように、自分のやりやすい方法で毎月の収支の変化を把握しておきましょう。
誕生月にねんきんネットを確認する
年金の支払い状況を確認すると、節税につながることがあります。それは年金の未納分を納める追納です。
追納は一カ月単位で支払いができますので、細かな金額調整ができる節税方法の一つです。
未納年金の有無を確認する方法は2つ、「ねんきんネット」と「ねんきん定期便」です。
ねんきんネットに登録すると、ペーパーレスによりねんきん定期便が送られて来なくなるため、年金の納付状況について確認する機会は減ってしまうかもしれません。
そこで、ねんきんネットを毎年の誕生月に確認する癖をつけるようにしておきましょう。
ただし追納時は、基本的に元々の保険料よりも高くなりますので注意してくださいね。
未納分を追納する
年金の未納分を追納すると、その金額が追納した年の社会保険料控除になります。
年金保険料の免除を受けたことがある方、これまで年金の納付履歴を確認したことがない方は一度チェックしてみてください。
※追納の期限は10年間です。
学生納付特例制度の追納をする
20歳になってから大学卒業まで年金を納めていなかった、という方は多いのではないでしょうか。
この期間は、申請することで学生納付特例制度が適用され、年金保険料の納付の猶予を受けることができます。
学生納付特例制度を受けた期間は老齢基礎年金の受給資格期間に含まれますが、年金額の計算対象となる期間には含まれません。
こちらも追納すると、その金額がその年の社会保険料控除になります。
※学生納付特例制度の追納ができるのは10年以内です。
未納期間についてはねんきんネットで確認し、年金事務所に納付書を請求してみましょう。
参考:日本年金機構ホームページ
まとめ
自営業の個人事業主やフリーランスは特に節税に関して意識していないと会社員以上に払う税金が多くなってしまいます。
まずは、毎月の収支を把握し、節税の裏ワザである控除を積極的に活用しましょう。
ご自身の経理状況を見直し、節税のために意識しみてください。
また、事業の規模が大きく、大きな額の節税をしたいと考えている方は以下の記事もおすすめです。