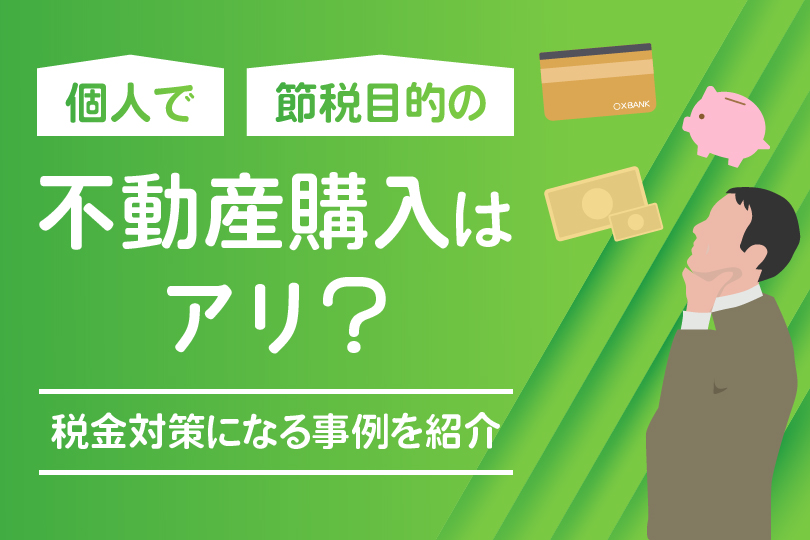給与明細から引かれている税金の金額が100万円を超えていた!となると、とても驚きますよね。
ふるさと納税やiDeCoでの節税や副業などを試したけれど、もっと他に方法はないか?と探していたところ、不動産投資という言葉を目にした方もいるのではないでしょうか。
この記事では、不動産投資が節税になるケースを紹介します。
また、不動産投資を始める前に確認しておきたい、居住用の不動産購入時の節税効果についても触れています。
ご自身の状況が不動産投資をすべき状況かを考えるきっかけになれば幸いです。
- 不動産投資によって節税できる4つの税金
- 不動産投資が節税になる3つの事例
- 自分に合った不動産投資の選び方
目次
不動産投資とは?

不動産投資とは、不動産を所有し、運用することで利益を出す投資行為です。
不動産投資には、不動産所得として家賃収入などで収入を得る不動産事業や、不動産を中心に運用する金融商品としてREIT(不動産投資信託)などがあります。
賃貸経営などの一般的なイメージ以外の不動産投資も含め、代表的なものを3つ紹介します。
1.賃貸経営
借家人が集まりそうな物件を購入し、賃貸物件として他者へ貸し出す方法です。
一般的にはワンルーム投資、戸建て投資などが挙げられます。その結果、オーナーとして家賃収入を得ることを目的とします。
不動産投資と聞いて最もイメージがしやすい方法かもしれません。
2.ホテル、駐車場経営
空いている土地や家、アパートを整備し不動産事業を営む方法です。
民泊やシェアハウス、サービス付き高齢者住宅など、時代によって様々な流行があります。
また、空いている土地を整備し、駐車場として貸し出した場合も不動産収入となります。
この場合、経営する施設の売り上げを収入として得ることを目的とします。
3.金融商品として販売されるREIT(リート)
実際に不動産を購入・保有せずに、間接的に不動産へ投資をする方法です。
一般的な投資信託と同様、運用はプロに任せるためREITを保有しているだけで不動産投資を可能にします。
運用実績によって分配金を受け取ることを目的とします。
住居以外にもオフィスや商業施設、ホテル、物流施設、病院や介護施設など、ジャンル分けされている商品を単一型、組み合わせたものを複合型と呼びます。
不動産投資で節税ができる税金の種類

不動産投資によって節税ができるパターンは2種類あります。
その中で、支払う金額を減らす事ができる税金は4種類あります。
- 不動産事業を経営する場合:所得税・住民税
- 不動産を他者に承継する場合:贈与税・相続税
それぞれシミュレーションをしながら見ていきましょう。
不動産投資が節税対策になる3つのケース
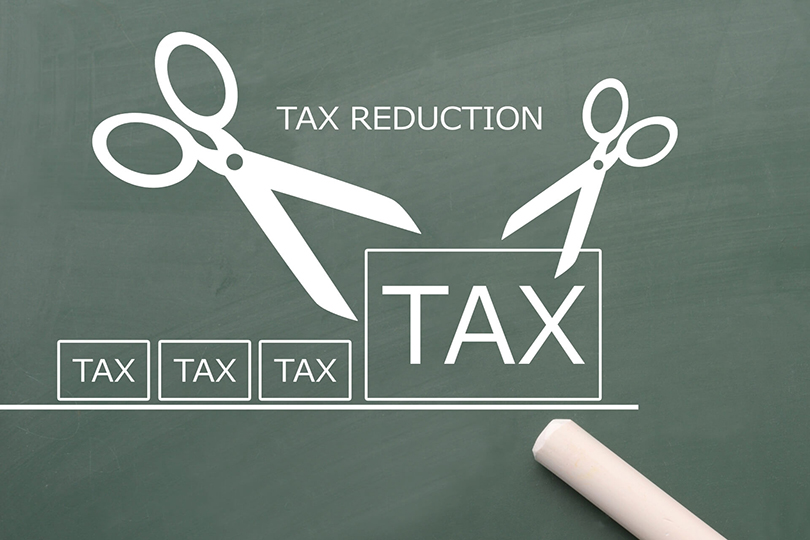
所得税・住民税を減らす
不動産事業を営み、収入よりも損失が多い状態にすることで総所得金額を減らす方法です。
不動産事業では、収入から経費や減価償却費などを差し引く事ができる点を利用します。
収入の多い所得と損失が生じた所得を合算することを損益通算といい、他の所得から赤字分を差し引くことで総所得金額を減らします。
節税になるとはいえ不動産経営としては赤字になっている分、支出があるということを忘れてはいけません。また、不動産の購入に係る借入金に対する利息は損益通算の対象外となるので注意が必要です。
この損益通算による節税は、所得金額が多い人ほど効果が得られます。
具体的に、給与所得330万円と900万円、それぞれの所得税額を比較してみましょう。
所得税の速算表
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000円 から 1,949,000円まで | 5% | 0円 |
| 1,950,000円 から 3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000円 から 6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000円 から 8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000円 から 17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000円 から 39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円 以上 | 45% | 4,796,000円 |
資料)国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)|No.2260 所得税の税率
例えば、賃貸経営の売上120万円に対してリフォーム代などの諸経費が200万円かかったとします。
不動産所得としては80万円の損失が生じています。
そこで損益通算を利用し、総所得金額から80万円分を差し引く事ができます。
(1)給与所得のみの場合
(2)給与所得と不動産所得の場合
2つのケースを比較してみましょう。
例1)給与所得900万円に対する所得税
(1)所得が給与所得金額900万円のみの場合
900万円 × 33% – 1,536,000円 = 1,434,000円
(2)所得が給与所得900万円と不動産所得80万円の損失の場合
(900万円 – 80万円) × 23% – 636,000円 = 1,250,000円
給与所得900万円の状態から不動産所得の損失額80万円を差し引くことで、所得税は184,000円の節税となります。
例2)給与所得330万円に対する所得税
(1)所得が給与所得金額330万円のみの場合
330万円 × 20% – 427,500円 = 232,500円
(2)所得が給与所得金額330万円と不動産所得80万円の損失の場合
(330万円 – 80万円) × 10% – 97,500円 = 152,500円
給与所得330万円の状態から不動産所得の損失額80万円を差し引くことで、所得税は80,000円の節税となります。
所得税と同様に住民税も損益通算を利用して節税することができます。
住民税は「所得割」と「均等割」という2種類の課税方法で構成されています。
このうち、均等割は一定以上の所得金額であれば全国一律ですが、所得割は前年の所得金額に比例して課税されます。
つまり、不動産投資で生じた赤字を給与所得等と損益通算することによって総所得金額が減り、住民税も節税することができます。
相続税・贈与税を減らす
相続を考えたとき、現金を不動産にすることで評価額を下げる方法です。
不動産の相続税評価額を判断する際には、小規模宅地等の特例が適用されます。
資産の評価額が下がると結果的に相続税が安くなることを利用します。
これは、相続税控除額を超えた資産を持っている方や、複数の土地を保有しているが活用できていない場合に効果が期待できます。
ただし、小規模宅地等の特例条件に当てはまるかどうか、相続人の了承が得られるか、相続人が不動産を引き継ぐ能力があるか、などは慎重に確認しておきたいポイントです。
また、居住用の不動産か事業用の不動産かによって減額割合が違います。
居住用では80%、事業用では50%~80%の減額がありますから、不動産投資を贈与や相続対策として活用することも一つの方法です。
仮に、120平方メートル5,000万円の戸建てを保有していた場合、居住用と事業用ではれぞれの評価額は以下のようになります。
居住用の場合
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等は、330平方メートルを限度に減額される割合は80%となります。
5,000万円 × 80% = 4,000万円
5,000万円 – 4,000万円 = 1,000万円
→相続税の課税価格に算入すべき価額:1,000万円
事業用の場合
被相続人等の貸付事業用の宅地等は、200平方メートルを限度に減額される割合は50%となります。
5,000万円 × 50% = 2,500万円
5,000万円 – 2,500万円 = 2,500万円
→相続税の課税価格に算入すべき価額:2,500万円
資料)国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)|
No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
生前に贈与を行う場合には「相続時精算課税制度」を利用することで、贈与税を抑えることが可能です。
相続時精算課税とは60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子・孫への生前贈与を行った場合に、確定申告を行うことで贈与者1人あたり最大2,500万円が非課税になる制度です。
賃貸物件であればそのまま保有していると、家賃収入は現金として蓄積されて相続税の対象となります。しかし贈与して家賃収入を承継すれば、将来の相続時の納税資金とすることができます。
ただし、相続時精算課税制度を利用すると、前述の小規模宅地の特例が適用されないケースがある点には注意が必要です。また、登録免許税と不動産登録税は相続時より高くなります。
申告分離課税で税率を減らす
金融商品であるREITを利用し、不動産投資の利益を配当所得として得る方法です。
これは、所得税・住民税が20%以上の税率になる方に限り効果がある節税方法です。
総合課税となる所得の一部を申告分離課税にすることによって、それぞれの税率が異なる点を利用します。
不動産を保有することが不動産投資だと思っていた方には意外な方法かもしれません。
具体的に、1,000万円の年利3%のJ-REITを保有し、配当を受け取ったときの違いをシミュレーションしてみましょう。
先にみたように、所得税は所得金額によって0%〜45%に区分されますが、株式などの配当所得を申告分離課税とした場合、税率は一律20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、地方税5%)です。
例)所得金額900万円(内REIT配当が30万円)時の所得税額
・所得金額900万円(内REIT配当の30万円を総合課税とする)の場合
900万円×33%-1,536,000円=1,434,000円
・所得金額900万円(内REIT配当の30万円を申告分離課税とする)の場合
870万円×23%-636,000円=1,365,000円
30万円×20.315%=60,945円
1,365,000円+60,945円=1,425,945円
所得の一部を申告分離課税とすることで、所得税額が8,055円の節税となりました。
資料)国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)|
No.2260 所得税の税率
No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
不動産投資と住宅ローン控除の比較

住宅ローン控除は、不動産投資の前に確認しておきたい節税方法の一つです。
住宅ローンに関する税額控除は、大きな節税になることで有名です。
不動産を投資目的ではなく、居住用の目的で購入することで得られる節税効果も考慮してみたいと思います。
例えば、3,000万円のローンを20年間で組んだ場合、毎月の返済額を10万円、年間の返済額を120万円した場合、受けられる住宅ローン控除額は以下のようになります。
10年間にわたって約18万円〜28.8万円の所得税額の控除を受けることができます。
| 1年目 | 残高2,880万円×1%=288,000円 |
| 2年目 | 残高2,760万円×1%=276,000円 |
| 3年目 | 残高2,640万円×1%=264,000円 |
| 4年目 | 残高2,520万円×1%=252,000円 |
| 5年目 | 残高2,400万円×1%=240,000円 |
| 6年目 | 残高2,280万円×1%=228,000円 |
| 7年目 | 残高2,160万円×1%=216,000円 |
| 8年目 | 残高2,040万円×1%=204,000円 |
| 9年目 | 残高1,920万円×1%=192,000円 |
| 10年目 | 残高1,800万円×1%=180,000円 |
※令和3年1月1日から令和3年12月31日まで1~10年目は年末残高等×1%(最高40万円)が税額控除
注意)住宅ローン控除の対象となるためには、以下の条件に当てはまる必要があります。
- 新築または、取得した日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること
- この控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること
- 床面積が50平方メートル以上であり、床面積の2分の1以上の部分が居住用であること
- ローン返済期間が10年以上あること
- それまで住んでいた家屋などについて、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
資料)国税庁ホームページ(https://www.nta.go.jp)|
No.1213 住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)
まとめ
不動産投資によって節税できる4つの税金は、所得税・住民税・相続税・贈与税です。
次に、不動産投資が節税になる3つの事例、不動産事業経営・相続贈与・配当を得る場合、それぞれの節税効果について確認しました。
最後に、節税という点から居住用の不動産購入による住宅ローン控除についても触れました。
不動産投資によって節税をしたいと考えたとき、さまざまな選択肢があって迷ってしまうと思います。
どの種類の税金を節税するのか、不動産を所有するのか、しないのかなど、目的に合った方法を知っておくことでより良い節税対策ができるのではないでしょうか。
この記事が、節税のために不動産投資をするかどうかを考えるきっかけになりますと嬉しいです。