青色申告・白色申告とは、確定申告の申告制度のことを指します。
青色申告は一定の要件を満たし、税務署長に承認申請書を提出、承認を得られた場合にさまざまな優遇を受けられる申告制度です。
一方、白色申告は青色申告の承認を受けてない場合の申告制度です。
青色申告の場合、総所得金額(所得=収入ー必要経費)から最大65万円を差し引くことが可能になり、課税される所得金額が低くなるという節税効果があります。
節税効果のほかにもたくさんの優遇を受けることができますが、さまざまな条件があります。
まず、それぞれの申告制度を利用する場合の手続き内容の違いを項目ごとに詳しく見てみましょう。
- 青色申告と白色申告の手続きの違い
- 青色申告と白色申告の節税効果
- 青色申告の優遇適用の条件
目次
青色申告・白色申告の手続き
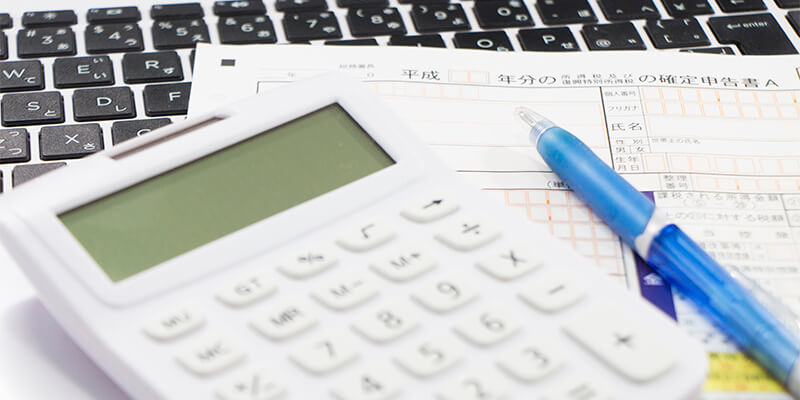
制度対象者
青色申告、および白色申告の制度対象となるのは、以下の方となります。
青色申告:以下の1~3の所得があり、青色申告の申請を行い、税務署から承認を受けた人
1、不動産所得…土地や建物などの不動産の貸付、船舶や航空機の貸し付けによる所得
2、事業所得…農業や漁業、製造業やサービス業、その他事業などを通じて得た所得のうち譲渡所得と山林所得を除いたもの
3、山林所得…山林を伐採して譲渡するか、立木のままで譲渡することによって生ずる所得
白色申告:上記の1~3の所得はなく、青色申告の申請を行わない人
税務署への手続き方法
青色申告:決められた期間内に納税地の所管税務署長に「青色申告承認申請書」を提出
白色申告:原則的な申告方法のため手続きは不要
申請書の提出期限
青色申告を利用する場合は、以下の期限内に申請し承認される必要があります。
- すでに事業開始済みで白色申告から変更する場合:青色申告を適用する年の3月15日まで
- 1月1日から1月15日までの間に事業を開始する場合:青色申告を適用する年の3月15日まで
- 1月16日以降に事業を開始する場合:事業開始日から2か月以内
白色申告は手続き不要で利用できるため、申請期限もありません。
次から、実際に青色申告でどのような優遇が受けられるか、白色申告との違いについて解説します。
青色申告・白色申告の優遇内容の違いと適用条件

青色申告と白色申告それぞれの優遇内容には、以下のような違いと適用条件があります。
青色申告特別控除
青色申告には、55万円(電子申告等の要件を満たした場合は65万円)または10万円の特別控除額があります。
単式簿記1つの科目で取引を記録(単式簿記)で記帳した場合の控除額は10万円になります。
55万円の控除を受けるためには、帳簿記帳の際「借方(かりかた)」「貸方(かしかた)」という概念を用いた腹式簿記で取引を記録します。そして損益計算書と貸借対照表を作成し、確定申告時に添付する必要があります。
複式簿記の例:〇月〇日に消耗品費を 1,000円、現金 で支払った場合
〇月〇日 消耗品費 1,000/ 現金 1,000
※消耗品を購入したことで消耗品費が増えて、現金が減ったことを表しています。
複式簿記は消耗品という費用が発生した場合は左側(借方)、消耗品購入のため現金が減った場合は右側(貸方)に記載するという記帳方法です。
白色申告は青色申告特別控除の適用は受けられません。しかし、すべての納税者に対して行われる「基礎控除」は受けることができます。
また、事業所得者には記帳が義務づけられるようになっていますので、確定申告の時に簡易帳簿の提出が必要です。
青色事業専従者給与と事業専従者控除
まず、事業専従者とは以下の条件に当てはまる人を指します。
- 生計を一にする配偶者やその他の親族である
- その年の12月31日時点で15歳以上である
- 年間で6ヵ月を超えて、その申告者が行う事業に従事している
また、上記の条件で従事している人に支払った給与が専従者給与になります。
青色申告では一定の要件で支払った給与を必要経費とすることができ、青色事業専従者給与控除として所得金額から差し引くことができます。
青色事業専従者給与には上限の設定はありませんが、妥当とされる金額を設定する必要があります。また、青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要になります。
白色申告では支払った給与額を必要経費とすることはできません。
しかし、従事している家族の人数、配偶者かその他の親族かの別、所得金額に応じて計算される金額を必要経費とみなし、事業専従者控除として差し引くことができます。
なお、白色専従者控除の金額は以下1・2の、どちらか低い金額になります。
1、事業主の配偶者なら86万円、配偶者以外なら専従者一人につき50万円
2、この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足して割った金額
貸倒引当金
取引先に商品やサービスを提供した時点では代金は受け取らずに、後で受け取る取引に掛取引があります。
貸倒引当金とは、掛取引の代金の回収ができなくなってしまうことを想定して、事前に金額を見積もり準備しておくお金のことです。
青色申告ではこの貸倒引当金の見込額(売掛金や貸付金を合計した5.5%以下)を一括して必要経費として、所得から差し引くことができます。白色申告の場合は取引先の倒産など、回収不能が確実な場合にのみ必要経費とすることが可能です。
損失の繰越し
「事業所得」「不動産所得」「山林所得」で発生した損失は、翌年以降に繰越すことができます。
また「事業所得」「不動産所得」「山林所得」で発生した損失は、他の黒字の金額と相殺します。これを「損益通算」といい、この制度は青色申告でも、白色申告でも利用することができます。
損益通算で相殺しても損失が残ってしまった場合、青色申告は、その損失額を翌年から3年間繰越して控除することができます。白色申告の場合は変動所得(※1)、または被災事業用資産の損失額(※2)に限り繰越しすることができます。
※1 漁獲・印税や原稿料など年々の変動が著しい所得
※2 事業用の資産が風水害、火災、震災等の災害で被害を受けたことによるもの
少額減価償却資産の特例
減価償却資産とは建物、車、備品等の事業用の資産で、購入金額が10万円以上の耐久性のある資産のことを言います。
本来、減価償却資産は購入した年に全額費用計上せず、耐用年数に応じて費用を案分します。
青色申告の場合、少額減価償却資産の特例を利用して、30万円未満の少額減価償却資産については購入した年に一括して費用計上することができます。
白色申告の場合は10万円未満の原価償却資産までしか一括して費用計上することができません。10万円以上の減価償却資産については、固定資産として費用計上します。
低価法の選択
棚卸資産(在庫)は、年度末に評価を行う必要があります。評価方法には「原価法」と「低価法」の2種類があります。
低価法を利用すれば、原価法による評価方法よりも売上原価(売上高に対する原価)を高く計上できる場合があり、その分事業所得が低くなることから、結果的に税金を低く抑えることができます。
青色申告では低価法を選択することができますが、白色申告では選択することはできません。
家事按分
自宅をオフィスとして使用している場合、家賃、光熱費、インターネット代、電話代など事業にかかった費用を計上することができます。
家事按分の分け方に決まりはありませんが、全体の費用のうち割合を算出するには、明確な根拠が必要です。
青色申告の場合は事業に関わる割合の決まりはなく、計上することができます。 白色申告の場合は事業に関わる部分が50%以上と区分できなければ、計上することはできません。
2020年分の確定申告から青色申告特別控除と基礎控除の金額が変更に

2020年分の確定申告から、青色申告特別控除と基礎控除の金額が変更になります。
- 青色申告控除額:65万円→55万円
- 基礎控除額:38万円→48万円
そして、55万円に改訂された青色申告特別控除の適用要件に加え、e-Tax(※3)による申告または電子帳簿保存(※4)を行うと、青色申告特別控除の金額は65万円になります。
※3 申告などの国税に関する各種の手続きする際に、インターネットを利用して電子的に手続きを行うことができるシステムのこと。
※4 一定の要件の下で帳簿を電子データのまま保存できる制度。
まとめ
青色申告は優遇される特典がたくさんありますが、事前の申請が必要であったり、確定申告時に提出書類が多く「複式簿記」での記帳が必要であったりと、簿記の専門的な知識がないとなかなか難しいと感じるかもしれません。
白色申告は事前に申請するものはなく、記帳方法も「単式簿記」で良いとされているため、シンプルで簡単に作業を完了させることができます。ただし、青色申告と比べ優遇される特典は少なくなります。
青色申告と白色申告のどちらで申請した方がいいかは、状況によっても異なります。
少しでも節税したいと考えるのであれば青色申告、手続きが簡単なほうが良い場合は白色申告を選択するのも良いでしょう。
ご自身の事業規模や状況に合わせ、賢く選択したいですね。

