「投資」と聞いて、何種類くらいの数を思いうかべますか?
身近な金融機関で投資できる金融商品や不動産以外にも、今はインターネットを介して投資できる、さまざまな種類の投資対象が存在します。
一口に投資といっても、その特性や投資対象・商品ごとにリスクやリターンも異なり、自分はいったいどれに投資すればいいのか悩む方も多いです。
しかし、どの投資が最適かはその方の資産状況や投資目的、投資期間などによって異なります。
たとえば、将来の年金不足分を補うための老後資金作りを目的として投資をするのに、株式の短期売買を繰り返す投機的な投資や、FXや仮想通貨などのハイリスク投資などはおすすめできません。
今回はリスクとリターンを代表的な投資種別ごとに比較し、できるだけリスクを抑えるために、投資をする際にできることなどについて解説します。
- 投資におけるリスクとリターンの意味や関係性
- 投資種別リスクとリターンの比較
- できるだけリスクを抑えるためにできること
目次
投資におけるリスクとリターンの意味や関係性
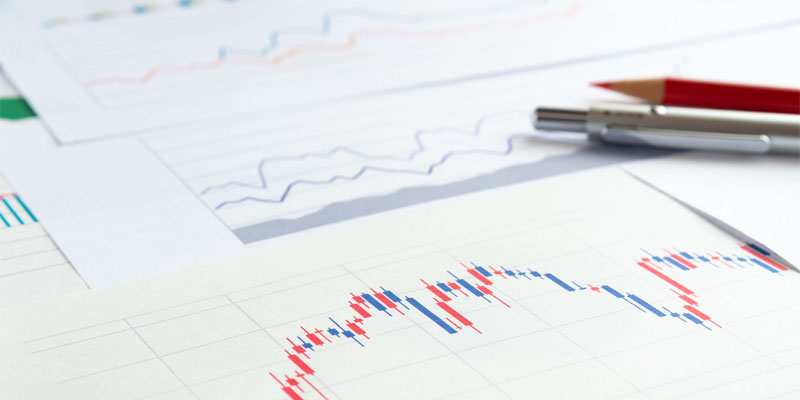
リスクの種類を知ろう
最初に、投資におけるリスクについてみていきましょう。
「リスク=危険や損失」と認識されることが日本では多いようですが、それは違います。投資におけるリスクとは「リターンの変動(ブレ)」のことを指します。
そして、一言にリスクといってもさまざまな種類があります。投資をする際は、自分が取ろうとするリスクがどのような内容なのかを正しく理解しておくことが重要です。
代表的なリスクは5つ。
1.価格変動リスク
株式の価格や投資した商品の値段が買値から上下する可能性のこと。
株式の価格の変動や、日本以外にも世界各国の景気や経済の動向、政治や経済情報のほか、株式投資の場合は株式を発行している企業の業績など、さまざまな要因によって起こります。
2.信用リスク(デフォルト・リスク)
株式や債券などを発行している国や企業が、経営不振や財政破綻するとなどを理由に投資家から預かっていたお金の一部または全額を返済する能力がなくなる可能性のこと。
たとえば、倒産した企業の株式が売買できず紙屑同然になることや、国が発行する債券が債券不履行(デフォルト)状態に陥る状態のことです。
直近の2020年5月22日にアルゼンチンが、グローバル債の利払いを行わなかったとして債務不履行(デフォルト)になったのも、記憶に新しいのではないでしょうか。
投資において、企業や発行体の信用リスクはとても重要になります。よく調べてから投資をしましょう。
3.流動性リスク
投資対象の市場(マーケット)で、持っている金融商品を売りたいときに買う相手が現れず売ることができなかったり、希望する値段で売れなかったりする可能性のこと。
特に株式投資では、小型株と呼ばれる市場全体の株主の数が少ない銘柄や、もともと大株主と呼ばれる基本的に売買しない株主の比率が高い企業の株式は、流動性リスクが高くなるため注意が必要です。
4.金利変動リスク
金利の変動によって、債券の市場価格が変動する可能性のこと。
基本的に、金利が上昇すると債券価格は下落し、金利が低下すると債券価格は上昇します。
しかし、2008年のリーマンショックや直近のコロナショックなどの金融市場に与えるインパクトが大きい金融危機の場合は例外で、株式も債券価格も同時に下がる場合があります。
5.為替変動リスク
異なる通貨の為替相場の動きにより、外貨建ての円換算による金融商品の価値または価格が変動する可能性のこと。各国の金利差や情勢、経済などさまざまな要因により為替は変動します。
リターンの本当の意味
リスクの次は、リターンについてみていきましょう。
リターンとは、投資を行うことで得られる収益または損失のことです。一般的にリターンというと収益のみをイメージする方も多いですが、投資を行った結果損失になった場合もマイナスのリターンになります。
そして、リスクとリターンは表裏一体の関係といえます。「リスクが大きいものほどリターンが大きい(ハイリスク・ハイリターン)」「リスクが小さいものほどリターンが小さい(ローリスク・ローリターン)」という傾向があるからです。
投資対象によってリスクやリターンの大きさもさまざまですが、基本的にリターンに見合ったリスクとなります。そのため「ローリスクでハイリターンが望める」などと謳った金融商品は、疑ってかかった方が良いでしょう。
また、複雑な仕組みの金融商品は自分が認識している以上にリスクが大きくなる可能性があります。オプション取引やデリバティブといった金融工学を利用した手法も、一部リスクをさらに大きくする運用方法ですので、投資する前によく確認しましょう。
代表的な投資の種類とリスク・リターンの比較

まず始めに、代表的な投資の種類と種別ごとのリスクとリターン、特徴をご紹介します。
| 投資対象 | リスク | リターン | リスクの種類 | 特徴など |
| 日本の個人向け国債 | ★ | ★ | 信用リスク 金利変動リスク | リスクが少なく、購入後1年経過すれば解約が可能。外国の債券の場合は為替変動リスクも有。 |
| 投資信託/ETF (上場投資信託) | ★★★ | ★★★ | 価格変動リスク 信用リスク 為替変動リスク 価格変動リスク 流動性リスク | 投資対象は国内外、株式や債券、REITなどさまざまな金融商品の中から選択可能。運用をプロに任せることができるが、買付時や保有期間中にコストがかかる。 ※一部レバレッジを効かせた投資信託やETFはリスクが大きくなる |
| REIT (不動産投資信託) | ★★★★ | ★★★★ | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク | 少額から行える不動産投資。現物の不動産ではなく証券化された不動産に対して投資をする。 |
| 株式投資 | ★★★★★ | ★★★★★ | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク 為替変動リスク | 上場している企業が発行する株式に投資。株価の変動が大きいため、リスクは大きいがリターンも大きい。 株主は出資した金額上の損失はないが、最悪企業が倒産し上場廃止になると価値0になる可能性もあり。 |
| 暗号資産(仮想通貨) | ★★★★★★ | ★★★★★★ | 価格変動リスク 流動性リスク 信用リスク ※取引口座から出金できないリスクもある | ビットコインに代表される、インターネット上でならどこでも誰でも売買できる通貨。一部店舗では暗号資産で決済可能。投機色が強く、値段はかなり乱高下する。リスクがかなり大きいがリターンも大きい。 ※一部取引会社によっては、口座からの出金に応じないところもあるので注意が必要。 |
代表的な5つの投資対象についてみてきましたが、それぞれ表をみて分かるようにリスクとリターンの大きさは一緒です。
ご自身の投資目的や望むリターンを考えて、そのリターンに見合ったリスクが取れるのかよく考えてみてください。
投資対象の選び方
リスクをより客観的に評価するには、債券であれば格付け会社と呼ばれる米国系の「ムーディーズ」や日本の格付け投資情報センター(R&I)などが、リスク分析をして「AAA(トリプルエー)」などとアルファベットや数字などの、簡単な記号でランク付けをしています。
投資信託であれば、格付投資情報センター(R&I)が中立・校正の立場から各投資信託のリスクの大きさで分類し、RC(R&I投信リスク・クラス)、を公表しています。
分類はリスクの小さい順に、RC1~RC5までの5段階評価で行われますので、投資信託を選ぶ際に参考にするのも良いですね。
もう1つ、投資信託や株式などでリスクがどの程度かを数字で表すものとして「標準偏差」があります。
投資における標準偏差とは、リターンのばらつきを統計的に示した数値です。
株式や投資信託の価格変動リスクを測るのに用いられ、数値が大きいほど価格変動リスクが大きくなります。標準偏差が小さいということはリターンの変動幅が小さく、標準偏差が大きいということはリターンの変動幅が大きいということです。
しかし、標準偏差はあくまで過去のデータを元に計算しているので、将来のリスクを表すものではありません。そのため、数値は参考程度に考えるのがよいかもしれません。
できるだけリスクを抑えるためにできる3つのこと

それでは、できるだけリスクを抑えて投資をするには、どうしたらいいでしょうか?
ここでは、投資をおこなうときにできる3つの方法を解説します。
できることその(1):自分が許容できる範囲のリスクを知ること
基本はリターンにみあったリスクを取ることになるので、求めるリターンを自分が許容できる範囲のリスクを取れるくらいに抑えることが必要になります。
リスクが小さくなるとリターンも小さくなるので難しいところですが、リスク許容度と呼ばれる中長期的な資産形成を目指すにあたり、どの程度の価格のブレや不確実性を自分が受け入れられるか、を知っていることも大事です。
リスク許容度は、経済的な資産状況や投資に対する考え方、価格のブレに対する精神的耐性の強弱によっても変わります。
しかし、こればかりは自分で実際に投資を経験してみないと正確には分かりません。
例えば、価格のブレが上下20%なら耐えられるけれど50%、特に下に動いた場合は精神的に落ち込んでしまい耐えられない。これ以上下がりそうで怖くて売却してしまう、などの精神的・現実的行動をしてしまう可能性もあり得ます。
投資初期の頃は、誰しも価格が下がっていくことに不安を感じやすくなります。そこを乗り越え、経験値とリスク許容度を徐々に増やしていけると良いですね。
できることその(2):投資対象について理解すること
2つ目に大事なことは、自分が投資しようとする投資対象について理解しているかということです。
中身すべてを完全に理解することは難しいですが、ある程度何に投資をしているのか、どんなリスクがありどの位のリターンを望めるのかは、確認してから投資をしましょう。
自分がよく理解していない金融商品に投資をするのが一番危険です。
できることその(3):時間・投資対象・地域を分散すること
そして、リスクを抑えるのに有効な3つ目の手段が、投資期間を長期間とることと、時間や投資対象・地域を分散することです。
特に、ドル・コスト平均法と呼ばれる時間分散の手法は、一括で商品を購入せず、資産を分割して均等額を定期的に継続して投資するため、相場の上がり下がりがあっても買値が分散・平均化され、相場に負けにくくなるという研究結果も発表されています。
また、投資対象や地域を分散することで、特定企業や商品、国や地域の政治的経済的情勢に関係なく、一定の利益を確保することが可能となります。
投資資金との兼ね合いもありますが、できるだけ投資する時間、対象、地域を分散するような商品選択を検討してみましょう。
まとめ
投資におけるリスクとリターンの意味と、代表的な5種類の金融商品のリスク・リターン比較、リスクを抑える方法について解説しました。
投資を行う際、どうしても利益がどのくらい挙げられるかに意識が行きがちですが、大切なことは長期間に渡って安全に投資し続けることです。 改めて、ご自身が投資されている商品のリスクとリターン、そして中身を確認して長期投資による資産形成に役立ててください

