相続税の節税対策として、生前に資産を贈与しておく生前贈与があります。不動産や貯金といった資産が対象ですが、仮想通貨も生前贈与することが可能です。
この記事では、仮想通貨の生前贈与について解説します。
仮想通貨の生前贈与で期待できる節税効果やメリット、贈与する際の注意点について解説していますので、ぜひ最後までお読みください。
目次
仮想通貨の生前贈与で節税対策

相続の対象となるのは土地や貯金といった資産ですが、仮想通貨も相続対象です。仮想通貨を生前贈与しておくと、相続税の節税効果が期待できます。
故人が仮想通貨を所持していた場合、相続人が仮想通貨を相続し、相続税が課せられます。生前に仮想通貨を贈与しておくことで遺産が少なくなり、相続税の節税につながります。
ただし、生前贈与をする際、年間110万円を超えてしまうと贈与税の課税対象となるので、注意が必要です。
仮想通貨は生前より相続時に、価格が大幅に値上がりしていることも考えられます。そうなると相続税が膨大になる可能性がありますが、生前贈与しておけば受贈者の資産にすることができます。
仮想通貨は登記されていないため、不動産のような登記の手間や手数料がかからず、比較的簡単に財産移転できるという点もメリットです。
また、ペーパーウォレット以外のWeb上のウォレットに仮想通貨を保管している場合、相続人がパスワードを把握していないと引き出せなくなってしまいます。相続時のトラブルを防ぐためにも、生前贈与を検討してみることをおすすめします。
仮想通貨を生前贈与する際のポイント

仮想通貨を生前贈与する際は、以下のポイントに注意が必要です。
- 贈与契約書を作成する
- 基礎控除額110万円を超えないようにする
- 受贈者のITリテラシー
仮想通貨の生前贈与で気をつけるべきことについて、以下より解説します。
贈与契約書を作成する
1つめは、贈与の際に贈与契約書を作成することです。
民法では、契約書のない贈与は撤回できると定められています。贈与があったことを証明できるよう、契約書を作成することが重要です。
また、税務署から贈与の事実を否認され、余計な課税をされてしまわないためにも、贈与があったことを証明できる契約書を作っておくことをおすすめします。
基礎控除額110万円を超えないようにする
2つめは、基礎控除額である110万円を超えないようにするという点です。
贈与には税金はかかりませんが、贈与税が非課税となるのは年間110万円までです。年間110万円を超えると贈与税の課税対象となってしまうので、注意が必要です。
また、受け取った仮想通貨を、受贈者が贈与された時よりも高い価格で売却して利益が発生した場合は、受贈者自身が所得税の申告をする必要があります。
生前贈与したい仮想通貨が年間110万円を超える場合は、年間110万円を超えない範囲で毎年生前贈与を行う、暦年贈与がおすすめです。
受贈者のITリテラシー
3つめの注意点は、仮想通貨の贈与はパソコンやスマートフォンを用いて行うため、ITリテラシーが必要となるという点です。
贈与を行うにあたり、受贈者にITリテラシーがあり問題なく手続きができるかどうかも確認しておくのがおすすめです。
仮想通貨の相続税評価方法
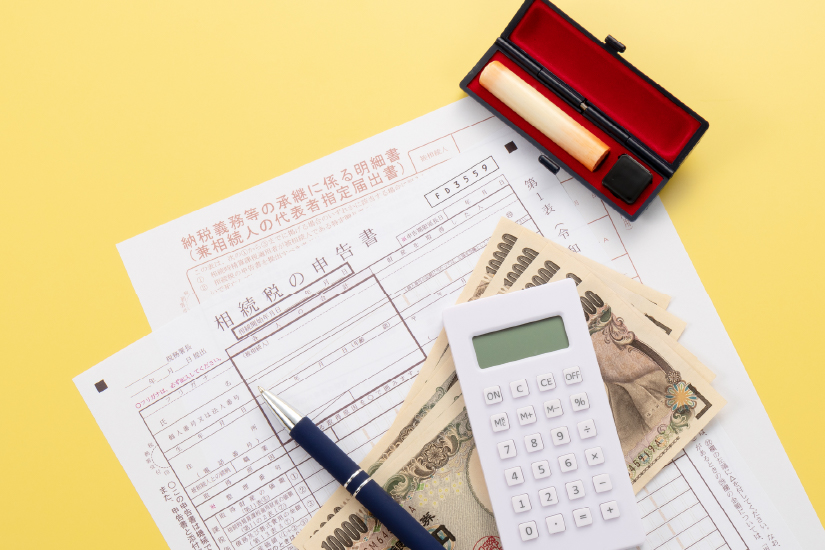
仮想通貨は、相続税の評価方法が明確に定まっているわけではなく、「評価方法の定めのない財産の評価」に該当します。
仮想通貨の相続税評価は、「活発な市場が存在する場合」と「活発な市場が存在しない場合」とで評価方法が異なる点が特徴です。それぞれの場合の評価方法について、以下より解説します。
活発な市場が存在する場合
贈与する仮想通貨について活発な市場が存在する場合は、以下の方法で評価されます。
- 仮想通貨の取引所が公開している課税時期の売却価格
- 相続人が取引所に申請して発行してもらった残高証明書
該当する市場が活発な市場かどうかは、取引量や頻度、価格情報が継続的に提供されているかどうかによって判断されます。
仮想通貨取引所の1つで、国内で最大級の規模を誇るbitFlyerでは、2021年時点で、以下の仮想通貨において活発な市場が存在していると定義しています。
- BTC(ビットコイン)
- ETH(イーサリアム)
- BCHN(ビットコイン・キャッシュ)
- LTC(ライトコイン)
- XRP(リップル) など
参照:計算書類(第8期)
活発な市場が存在しない場合
取引量や頻度が少なく、価格情報が継続的に提供されていない場合、活発な市場ではないと判断されます。その場合は、仮想通貨の内容や性質、取引実態を個別に評価して相続税を決定します。
まとめ
相続税の節税対策のため、仮想通貨を生前贈与するという方法があります。仮想通貨を生前贈与する際は、贈与税がかからないよう年間110万円に抑えるか、年間110万円以下の範囲で暦年贈与を行うのがおすすめです。
贈与を行う際は、贈与契約書を作成しておくことをおすすめします。
節税ハックでは、さまざまな節税方法について解説しています。また仮想通貨以外の投資方法やリスク分散方法、投資信託の選び方についても解説していますので、合わせてご覧ください。

