会社の資本金を増やす「増資」を検討している会社の多くは、増資によって税金にどう影響するのかを気にしているのではないでしょうか。
節税を意識することは会社経営において欠かせないものであり、増資に伴って節税効果が得られればと期待するのは当然のことです。
ここでは、増資の方法と注意点を踏まえた上で、節税効果が期待できるのかを解説します。
目次
資本金増資による節税効果はある?
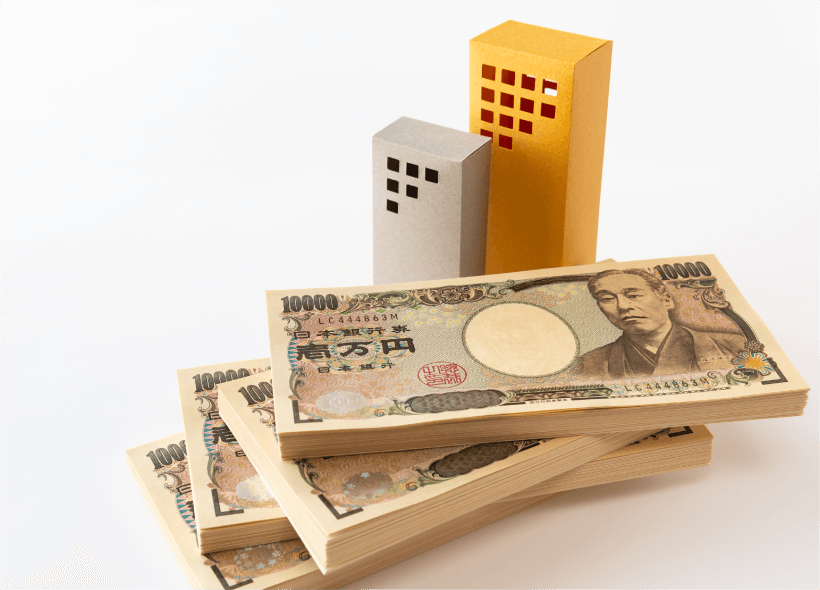
事業の元手となる資本金は、「会社の体力値」とも呼ばれ、その会社の信用力を高めるために増資を検討する会社も少なくありません。また、出資を受けることが決まっているため増資をするという会社もあるでしょう。
増資は会社にとってメリットがあるものですが、節税対策の観点からみると、節税効果があるとは言い切れないのが実情です。
税金は会社にとって大きな支出となるため、税負担を積極的に軽減することで会社の利益がより多く残ることになります。
節税は会社の儲けにも繋がるものですが、増資することで税負担が増すこともあるのです。基本的に節税を目指すのであれば、資本金を増やすのではなく減らす、減資が選択肢に挙げられます。
会社が抱える事情にも左右されますが、増資をするのであれば一度増資し、その後減資するという選択を取る方が節税効果を得られる可能性が高いと言えるでしょう。
資本金増資の基礎知識

資本金増資とは
資本金増資とは、会社を設立した後に資本金を増やすことを言います。
会社設立後に資金を増やすには、主に二つの方法があります。一つが銀行からの融資、もう一つが増資です。
資本金は事業を円滑に進める元手となる資金のため、新規事業を立ち上げるなど、さらに資金が必要となった際は増資によって資金を調達する会社も多いでしょう。
資本金増資の方法と手続きについて
資本金増資には様々な方法があります。ここからは具体的な増資方法と手続きについて紹介しましょう。
資本金増資には大きく二つの方法があります。
一つめが、「株式の発行による増資」です。株式の発行により出資者を募り、出資者から資金を集める方法です。株式の発行による増資には主に三つの方法に分かれます。
株式の発行による増資の方法
株主割当増資
株主割当増資は、既に会社の株式を持っている株主に対して新たに株式を購入してもらう方法です。
既に保有している株式の数に応じて均等に出資してもらうもので、多くの株式を持っている株主にはそれに応じて多くの出資をしてもらいます。
既存の株主に対して理解を得るために、株主総会を開く必要があります。
第三者割当増資
第三者割当増資は、株主割当増資ができない場合に採用されることが多い増資方法です。
合併や買収でも使われている方法で、新たに株式を発行することにより、これまでの持株比率が変わる可能性があるため、株式の発行数や既存の株主との関係性に注意が必要です。
公募増資
公募増資とは、既存の株主や特定の第三者に限らず、一般の投資家を対象に広く出資者を募る方法です。
資本準備金の利用による増資の方法
資本金増資の二つめの方法は、「資本準備金の利用による増資」です。資本準備金とは、会社法第445条2項によると、「資本金の2分の1を超えない金額に関して、資本金として計上しなくてもよい部分」のことです。
赤字の補填など、万一の際に備えたお金を意味します。この資本準備金の一部またはすべてを資本金に組み入れることで、増資ができます。
ただし元々資本準備金として会社が保有していた資金のため、会社の資金自体は増えていない点が株式による増資との違いです。
「株式の発行による増資」の場合は、株主総会での決議や、株主を募り、株式を購入してもらうための手続きが必要となります。具体的な流れとして、株主割当増資の例を挙げてみましょう。
- 取締役会・株主総会の決議
- 株主への募集事項等の通知
- 株主からの引受けの申込み
- 株主が資本金を払い込む
- 登記申請
「資本準備金の利用による増資」の手続きは、資本準備金の一部を資本金に組み入れる場合、「株主総会の普通決議」と「債権者保護手続き」が必要です。
資本準備金のすべてを資本金に組み入れる場合のみ、「株主総会の普通決議」だけで手続きが進められます。その後、資本組み入れの登記申請を法務局に行います。
資本金増資による節税効果と注意点

資本金増資による節税効果
資本金は1,000万円未満であれば、法人税や消費税の節税となります。
増資する場合も、節税を意識するのであれば1,000万円未満に抑えることがポイントとなるでしょう。具体的にどれくらいの節税になるのか、紹介していきます。
法人税の減税効果
法人税は所得と法人税率を掛けて計算します。資本金が1億円以下の法人について、課税所得800万円までは15%の軽減税率が適用されます。
課税所得が800万円を超える部分については税率が23.2%になるため、法人税の観点からは、資本金は1億円以下であれば優遇税率の恩恵が受けられるでしょう。
法人住民税の減税効果
法人住民税は法人税割と均等割の合計額によって算出されます。均等割は資本金をベースに決められ、資本金が多いほど課税額が高くなります。
均等割の最低額は7万円で、資本金等が1,000万円を超えると金額が上がり、会社が赤字であっても発生する税金です。
節税を目指すのであれば資本金をできるだけ抑える方が、納税の負担が少なくなるでしょう。
資本金増資に伴う注意点
基本的に資本金が多ければ多いほど納めなくてはならない税金が増えます。
しかし、どの税金がいくらかかっているのか把握し、資本金を調整することで免除される税金もあります。
資本金増資による所得税の課税
資本金が1,000万円未満であれば、会社設立後最大2年間は所得税の納税が免除されます。
しかしその間に増資により資本金が1,000万円以上になると免除の対象外となり、所得税を支払う義務が課せられます。
消費税免税期間を最大限活用するには。資本金は1,000万円未満に抑えておくと良いでしょう。
設備投資の際の税額控除
中小企業の設備投資を後押しする優遇税制の中には、事業用設備等を購入した際に一括で損金計上できるという特例があります。
しかし資本金が3,000万円を超えると設備投資の際の税額控除が利用できなくなるため、注意が必要です。
その他、資本金が1億円を超えると法人事業税において外形標準課税制度の対象となり、さらに新たな税金が加わるため、どのくらい増資するのかがその後の会社のコストに大きく関わってくることが分かるでしょう。
まとめ
返済不要の資金が調達できる、会社の信用が高まるなど、増資によって得られるメリットも多い一方、増資によって税制の優遇が受けられなくなるリスクが生じる可能性もあります。
会社にとっては利益を生み出すのと同様に節税対策は重要です。
増資する際はいくらまで増資するのか、これまで受けてきた税制上の優遇は引き続き受けられるのかも把握して節税を意識した増資の検討することが大切です。

