「扶養」には「社会保険上の扶養」「税法上の扶養」との2種類があることをご存知でしょうか?
「社会保険上の扶養」とは、健康保険や年金に関するもので、被保険者の扶養に入ることで被扶養者も同様のサービスを受けることができるものです。
一方「税法上の扶養」とは、年末調整や確定申告で配偶者や扶養親族を申告することで、所得税や住民税といった税金の負担を軽くするものです。
今回はこの中から、税法上の扶養、主に扶養控除についてくわしく解説していきます。
- 扶養控除の基本と注意点
- 扶養控除の対象となる親族とは
- 子どもがアルバイトをする場合のボーダーライン
- 節税につなげるポイント
目次
扶養控除の基本と注意点
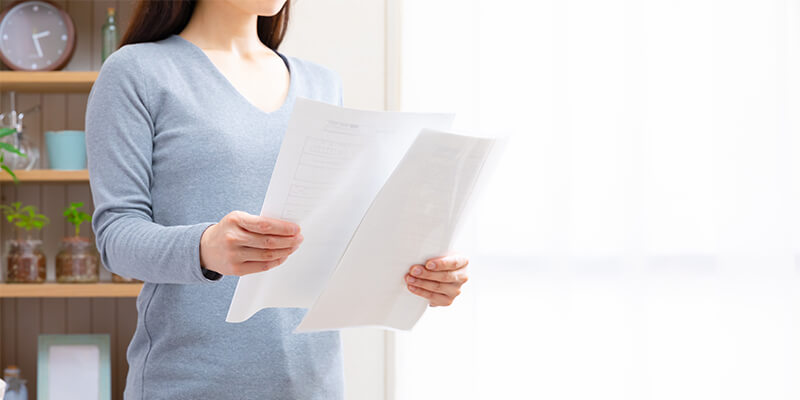
扶養控除とは、子供や親、親族を養っている場合に一定金額の所得控除を受けられる制度です。
家族を養っていたり、別居している親に毎月生活費を仕送りしていたりすると、その分生活費の負担が増えます。
そのような事情を考慮して、税法上の負担を軽くしようという措置が取られているのです。
配偶者は扶養控除の対象ではない
配偶者は、扶養控除の対象には含まれません。
よく「妻が夫の扶養に入る」などと表現されるため混同しがちですが、配偶者は「配偶者控除」または「配偶者特別控除」の対象となります。
「扶養控除」と「配偶者控除・配偶者特別控除」は別の控除であると認識しておきましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除とは、納税者に無収入または収入が少ない配偶者がいる場合に所得控除ができるものです。
これらの制度は平成30年より条件や控除額が大きく変更されました。
ポイントを絞ってみてみると、
- 控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入のみの場合は1,220万円)を超えると適用されない
- 控除額は納税者の所得区分によって段階的にかわる
などが挙げられます。
青色申告者の事業専従者や白色申告者の事業専従者は対象とならないため、納税者の経営している会社を手伝っていて給料を受け取っている場合などは注意が必要です。
対象となる場合はきちんと適用条件を確認し、税金の払い過ぎとならないようお気をつけください。
扶養控除の対象となる人の要件を全て満たす必要がある
扶養控除の対象となるには、その年の12月31日の時点で以下の要件を全て満たしている必要があります。
- 配偶者を除く16歳以上の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、また、いわゆる里子や市町村長から養護を委託された老人であること。
- 納税者と生計を一にしていること。
- 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)、給与のみの場合は年間の給与収入が103万円以下であること。
- 青色事業専従者として給与を受け取っていないこと、又白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁ホームページ「扶養控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htmを参考に作成
この要件のうち「生計をともにする」には、明確な決まりがあるわけではありません。
たとえば、以下のような場合は「生計をともにする」ものとして取り扱われます。
- 「仕事や学校の都合でやむなく別居しているが、休みの日は一緒に過ごしている」
- 「常に生活費や療養費を送金している」
つまり、別居している親族でも、その他の適用条件を満たしていれば扶養控除の対象となる可能性があるのです。
また、この他の注意点として「扶養控除の重複はできない」ことが挙げられます。
これはたとえば、兄弟がともに遠方で暮らす母に仕送りをしている場合、母を扶養控除の対象とできるのは兄弟のうち、だれか1人だけということです。
たとえ兄弟が同じ金額を仕送りしていても、扶養控除の対象とできるのは1人だけです。後々もめることのないように、事前に話し合って決めておくとよいでしょう。
扶養控除額は一律で、所得が多い方が節税効果は大きくなる
扶養控除額は納税者の所得を問わず、扶養親族の年齢や同居の有無によって一律で決まっています。よって、納税者の所得が多い方が節税効果は大きくなるのです。
扶養控除額を表にしたものがこちらです。
| 区分 | 年齢 | 控除額 |
| 一般扶養親族 | 16歳以上18歳以下 23歳以上69歳以下 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上22歳以下 | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上 | 58万円 |
| 老人扶養親族(同居以外) | 70歳以上 | 48万円 |
出典:国税庁ホームページ「扶養控除」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htmを参考に作成
表を参考に、扶養控除の注意点を3つ確認しましょう。
- 15歳以下の年少扶養親族は「児童手当」が支給されるため扶養控除の対象ではない。
- 「特定扶養親族」は、教育費がかかる大学生の子を持つ親の負担を軽減するため、控除額が高く設定されている。
- 老人扶養親族は「同居」か「同居以外」かで控除額が異なる。
このうち、老人扶養親族の「同居」とは、納税者またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で、納税者またはその配偶者と普段同居していることをいいます。
たとえば、病気の治療のために1年以上の長期入院をしており、納税者と別居している場合などは「同居」という扱いになります。
一方、老人ホームなどへ入所している場合には、老人ホームが住まいとなるため「同居」とはいえません。
しかし、老人ホームの費用を一定して支払っているなど「生計をともにしている」ことが確認できれば、扶養控除の対象となります。
子どものアルバイトは103万以下に留めると節税になる
アルバイトをしている高校生や大学生の子どもがいる場合、その親が扶養控除を受けるためには、アルバイトの給与収入が103万円以下(所得の場合は38万円以下、令和2年分以降は48万円以下)である必要があります。
では、もしその金額を超えてしまったら、どのくらい税金の負担に差があるのかみてみましょう。
所得税の計算方法は以下の通りです。
( 収入金額 ➖ 必要経費 ➖ 所得控除 )✖️ 税率 = 所得税
所得税の税率は、所得が多くなるにしたがって段階的(7段階)に高くなる「超過累進課税」の仕組みがとられています。
そのうち今回は、以下の所得金額別の事例を見ていきたいと思います。
アルバイト収入が103万円以下の18歳高校生の子を養っている : 7万6000円
アルバイト収入が103万円以下の20歳大学生の子に仕送りをしている: 12万6000円
アルバイト収入が103万円以下の18歳高校生の子を養っている : 15万2000円
アルバイト収入が103万円以下の20歳大学生の子に仕送りをしている: 25万2000円
お子様が扶養控除の対象となると、これだけの税金の負担が軽減されるのです。
一方で、アルバイト収入が103万円を超えてしまうと、これらの税金の軽減が0になってしまいます。
大学生になり一人暮らしを始めると、親子でコミュニケーションをとる機会も少なくなります。
「気がつかないうちにお子様のアルバイト収入が103万円を超えていて、扶養から外れてしまった」ということのないように、事前にお子様と相談しておくことが大切です。
扶養控除を節税につなげるポイント

上記の「子どものアルバイトの試算」でもわかる通り、扶養控除対象者が一人増えるだけで大きな節税となります。
以下に「見落としやすい扶養親族」を挙げました。
見落としやすい扶養親族とは
日本国外に住んでいる
確定申告時に必要書類を添付することで扶養控除の対象とすることが可能です。
別居の親がいる
別居の場合、つねに生活費を送金しているなど「生計をともにしている」ことが必要ですが、確定申告や年末調整で提出が必要な書類はありません。
しかし、正確な税額計算のため、また証明を必要とされた時に備えるため、手渡しではなく、銀行振込や現金書留など証明書が発行できる方法を利用されるのがいいでしょう。
遺族厚生年金や遺族基礎年金を受け取っている親がいる(生計をともにしている)
扶養親族を判定する場合の合計所得金額に、所得税法で非課税とされる所得は含まれません。
よって、遺族厚生年金や遺族基礎年金は所得に含まれないため、その他の要件を満たしていれば扶養控除の対象となります。
このほか「納税者の夫婦が、同居する親の扶養を、お互い相手が申告していると思っていたが実はどちらもしていなかった」など、何らかの理由でうっかり申告していなかったという可能性もあります。
大きな節税につながる扶養控除ですので、申告漏れはとてももったいないことです。
今一度、申告していない親族がいないか確認してみましょう。
払い過ぎた税金を取り戻すには、5年間の猶予がある
もし申告漏れで税金を払い過ぎた場合でも、間違っている旨を申告することで税金の還付が可能です。
この税金の還付は「年末調整をした場合」と「確定申告をした場合」で方法が異なります。
年末調整をした場合
会社員など年末調整を行っている方で、年末調整後に訂正が見つかった場合は「還付申告」を行います。
この還付申告は、確定申告の期間とは関係なく、修正が必要な年の翌年1月1日から5年間(たとえば、令和元年分の還付申告の期限は令和2年1月1日〜令和6年12月31日)おこなうことが可能です。
確定申告した場合
自営業など年末調整は行わない方で、確定申告後や還付申告後に訂正が見つかった場合は「更生の請求」を行います。
「更生の請求」をおこなえる期間は、確定申告の場合は、その年の法定申告期限(3月15日)から5年以内。還付申告の場合は、その提出をした日から5年以内となります。
いずれも修正期間は5年間と、比較的猶予がありますが、修正が必要とわかったら忘れないうちに早めに申告する方がよいでしょう。
まとめ
扶養控除には大きな節税効果があり、またその効果は納税者の所得が多いほど大きくなります。
また扶養控除には基本のルールの他に、
- 子どものアルバイトのボーダーラインに注意する
- 別居の親族や海外在住の親族も控除の対象となる可能性がある
- 遺族厚生年金や遺族基礎年金は扶養控除の所得計算の対象外
- 申告漏れがあっても、5年間訂正可能
など、いくつか気をつける点がありました。
年末調整や確定申告の扶養控除の申請は、毎年のことでついつい流れ作業になりがちですが、これらの点に気をつけて正しく節税効果を得られるようにしましょう。

