最近、よく目にする「つみたてNISA」と「iDeCo」。
利用することにより税金の負担が軽くなる制度です。
これらの制度の利用を検討する際にどうしても節税効果に意識が行きがちですが、もっと本質的な投資目的を考えた上で選択をする必要があります。
それを踏まえた上で、それぞれの制度のメリット・デメリットと、どちらがより節税効果があるか解説します。
- つみたてNISAのメリットとデメリット
- iDeCoのメリットとデメリット
- どちらの制度が、より節税効果があるか
目次
つみたてNISAとは

つみたてNISAは、少額からの長期・積み立て・分散投資を支援するための非課税制度で、2018年1月からスタートしました。
NISAの概要
| 利用できる人 | 日本に住んでいる20歳以上の方 |
| 非課税対象 | 一定の投資信託やETFから得られる分配金・譲渡益 |
| 口座開設可能数 | 1人1口座 |
| 非課税投資枠 | 新規投資額で毎年40万円が上限(非課税枠は20年間で最大800万円) |
| 非課税期間 | 最長20年 |
| 投資可能期間 | 2018年~2037年(※2024年の改正により2042年まで延長) |
| 投資対象商品(※) | 長期投資・分散投資に適した一定の投資信託またはETF |
※金融庁:つみたてNISA対象商品届出一覧
https://www.fsa.go.jp/policy/nisa2/about/tsumitate/target/index.html
つみたてNISAでは、毎年新規資金で40万円を上限として一定の投資信託やETFが購入可能です。資金を出資した年に購入した投資信託を保有している間に得た分配金は、購入した年から数えて20年間課税されません。
また、その投資信託を購入した年から20年の間に売却して得た利益(譲渡益)についても非課税になります。
2020年8月1日時点で、投資の譲渡益にかかる税金は利益に対して20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
たとえば、100万円の利益が出た場合、通常の投資での利益であればそこから203,150円が税金として引かれますが、つみたてNISAの場合は100万円の利益全額が手元に残ります。利益が大きくなればなるほど、非課税になる金額のインパクトは大きいですね。
非課税期間の20年間が終了したときには、NISA口座以外の課税口座に払い出しされます。つみたてNISAは、翌年の非課税投資枠に移すロールオーバーはできませんので注意してください。
つみたてNISAのメリット
つみたてNISAのメリットは、4つあります。
・譲渡益が非課税になる
通常、利益に対してかかる譲渡益は税金が20.315%かかります。それが非課税になるのが大きなメリットです。
・長期の資産形成に適している
非課税期間が20年と長いので、長期間にわたり非課税になるメリットが活かせます。
・シンプルな制度で分かりやすい
非課税の投資枠は年間40万円の範囲内、一定の条件に合致した投資信託を最長20年間にわたり積み立てることができる、その間に受け取る「普通分配金」や「解約した時の利益」が非課税になる、という比較的シンプルな制度で分かりやすいです。
・対象となっている投資信託の手数料水準が低い
金融庁が選んだ対象の投資信託は、2020年6月29日時点で157本。すべて購入時の手数料はゼロ(ノーロード)で、保有期間中にかかる手数料である、信託報酬の上限も一定水準以下に限定されています。
このように、つみたてNISAはシンプルな制度で非課税メリットを活かしながら、手数料水準が低めな低コストな投資信託をコツコツ積み立てていく制度になっています。
つみたてNISAのデメリット
つみたてNISAのデメリットについてもみていきましょう。
・分配金を再投資する場合は、追加購入とみなされる
投資信託で分配金が出る場合は、買付設定時にその分配金を受けとるか、再投資するかを選択します。
ただし、再投資コースを選択し、かつ、つみたてNISAの年間投資枠を積み立て分だけで上限40万円まで利用している場合、普通分配金が出た際に枠を超えてしまいエラーになるということも起こりえます。
・解約しても「非課税枠」は再利用できない
つみたてNISAは、年間上限40万円×20年で最大800万円の非課税枠を利用することができます。
しかし、積み立ててきた非課税分の投資信託を売却した場合、その枠を再利用することができません。また、iDeCoのように、保有商品を売却して別の商品を買い付けるスイッチングはできません。
もし、非課税枠を満額利用したい場合は、いままで積み立ててきた投資信託は保有したまま、新たに別の投資信託の積み立てを開始すれば非課税枠のスケールメリットを活かせます。
iDeCoとは
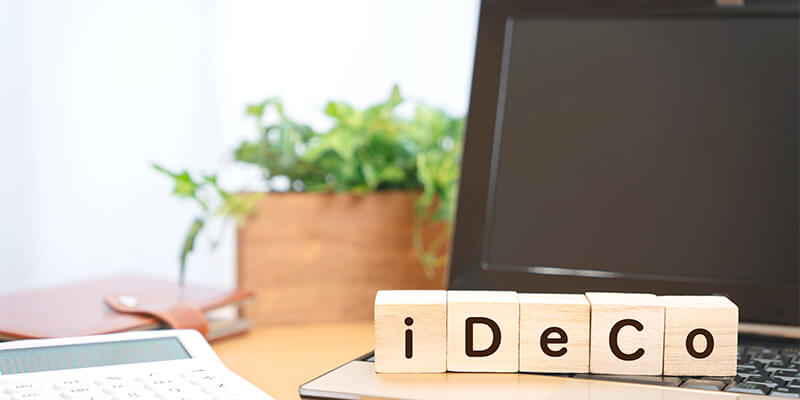
iDeCo(イデコ)とは個人型確定拠出年金の愛称で、自分が拠出した掛金を自分で運用し資産を形成する年金制度です。老後資金を貯めるための自分年金をつくることを目的とし、希望者が申込みをして任意で加入します。
掛金は60歳(2022年5月1日以降から65歳まで可能に制度改正)になるまで拠出しますが、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
iDeCoのメリット
iDeCoのメリットは、4つあります。
・所得税を払っている方であれば、掛金を拠出することで税金が安くなる(所得税、住民税)
iDeCoは毎月一定の掛金を積み立てますが、積み立てた金額すべてを所得控除の対象にすることができます。
・運用益も非課税
掛金だけでなく、運用中に金融商品を売却した利益に対しても非課税となるので、税金の負担が軽くなります。
・老後の備えとして「自分年金」が充実する
60歳まで引き出せないからこそ、老後資金用に半強制的にコツコツと積み立てて備えておくことができます。
・60歳以降の受け取り時にも税負担が軽くなる
iDeCoは受け取り方により、税負担が軽くなる場合があります。
iDeCoの受け取り方として「一時金」で受け取る方法と、分割して受け取る方法がありますが、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」、分割で受け取る場合は「公的年金等控除」の対象となります。
元々、退職所得は長年の勤務に対する報奨的給与としてまとめて支払われるものである、などの性質から税負担が軽くなるように配慮されています。そのため、iDeCoを一時金として受け取る際も同様に税負担が軽くなる場合が多いです。
iDeCoのデメリット
つぎに、iDeCoのデメリットについてもみていきましょう。
・60歳になるまで引き出せない
iDeCoで積み立てたお金は、60歳になるまで積立を停止することはできますが、引出すことができません。しかし、裏を返せばきちんと老後資金に手を付けずに運用できるというメリットにもなります。
・iDeCo専用口座の開設・維持に手数料がかかる
iDeCoを始めるには、銀行や証券会社などにiDeCo専用口座を開設する必要がありますが、その口座の開設時と維持に手数料がかかります。
初回の開設手数料はどこも同じで2,829円ですが、運用期間中にかかる毎月の費用(運用管理機関手数料)は金融機関によって大きく変わります。
2020年7月1日時点で、運用管理機関手数料が一番安い金融機関で月171円、高い金融機関で月629円とその差は458円。この金額は運用期間中ずっとかかるため、運用期間が長くなれば長くなるほど運用成績に影響を及ぼします。
ただし、運用管理機関手数料が高い金融機関であっても、利用者に対するサポートが手厚いなどの特徴がありますので、ご自分の投資経験や求めるサービスに応じて金融機関選びをおこないましょう。
つみたてNISAとiDeCo、どちらの制度をえらぶのがよい?

つみたてNISAとiDeCo、それぞれの制度の概要とメリット・デメリットを見てきましたが、それではどちらの制度を選ぶのが良いのでしょうか?
2つの視点から考えてみましょう。
節税効果から考える
「節税効果」の観点で見てみると、やはり「iDeCo」に軍配が上がります。
つみたてNISAは運用益だけが非課税なのに対し、iDeCoは掛金、運用益、将来受け取るお金のそれぞれが税優遇や非課税の対象となります。
特に大きな違いは、iDeCoは掛金を拠出した時点で税金を安くすることができる点です。
運用益の非課税メリットは利益をださないと享受できませんが、掛金は出すだけで税負担を軽くしますのでこの点は大きいです。
老後資金を準備する目的で、60歳以前に使う必要のないお金であれば節税メリットの大きいiDeCoを利用する方がよいでしょう。
資金の流動性から考える
「節税効果」という観点から考えると非常に効果が高いiDeCoですが、資金が60歳まで引出せないというデメリットがあります。
一方、つみたてNISAは非課税となるのは運用益だけですが、掛金や運用で得た利益は任意のタイミングで換金、出金することができます。つまり、こどもの教育費や住宅資金など、老後資金以外の資金をつみたてNISAを利用して準備することも可能です。
60歳までに使うお金を、運用益の非課税メリットを享受しつつ流動性を重視して準備しようとするのであれば、つみたてNISAを利用する方がよいでしょう。
まとめ
iDeCo、つみたてNISAそれぞれにメリット、デメリットが存在します。
そのため、節税効果という1つの観点から利用する制度を選択するのではなく、どのような目的で資金を準備したいのか、投資目的を考えた上で制度を利用するのが良いのではないでしょうか。
この2つの制度は併用して利用することが可能です。どちらか一方の制度だけを利用するのではなく、老後資金はiDeCo、子どもの教育費などの場合はつみたてNISAを利用するなど、柔軟に使い分けるのも一つの方法です。
節税は大事ですが、節税ファーストではなく、投資目的に合わせて制度を選ぶことでより効率的に資産運用ができるのではないでしょうか。

