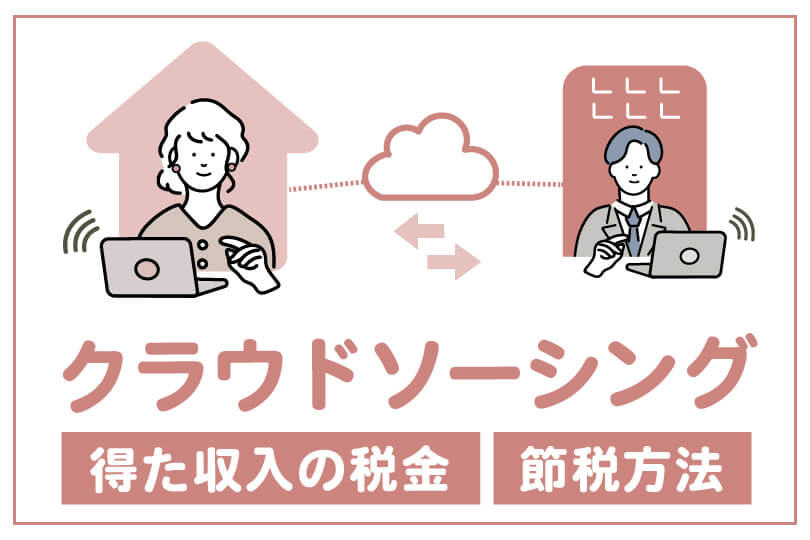1990年前後から日本企業に広まっていった経営手法の1つに「アウトソーシング」があります。「out=外部」と「sourcing=(材料などを)仕入れること」を組み合わせた言葉で、社外から人的リソースを調達するという意味では「外注」に近い意味です。
2000年代にはさらに「クラウドソーシング」というシステムが派生しました。主に個人に対して業務を委託する契約で、パソコンとインターネットを使用して募集から納品までを行います。
収入を得ると納税の義務が発生しますが、クラウドソーシングで得た収入に対する税金はどのようになっているのでしょう?この記事ではクラウドソーシングで発生する税金や節税の方法について解説します。
- クラウドソーシングの仕組みがわかる
- クラウドソーシングで得た所得に対する税金の扱いがわかる
- 税金の節税方法がわかる
目次
クラウドソーシングの仕組み

クラウドソーシングでは「クライアント」と呼ばれる発注者から業務を依頼して、「(クラウド)ワーカー」と呼ばれる受注者が業務を行います。その際にクラウドソーシングのサービスを取り扱う企業が仲介して、募集・受注・契約・支払いなどを行います。
この際に発生するお金の流れとして、クライアントからワーカーに支払われる「報酬」と、クラウドソーシングサービスを利用する「手数料」があります。
依頼と報酬
クラウドソーシングでは多くの場合、時給制や月給制ではなく、依頼に応じた成果物を納品すると報酬が支払われるシステムです。具体例としては以下のような依頼内容があります。
- 金融関係の記事(4,000文字)を3本
- Webサイトの新しいコンテンツを作成
- 指定したテーマの写真を20枚
利用した際にかかる手数料
ワーカーはクラウドソーシングサービスに対して、システム利用料を支払います。また、報酬の振込手数料が差し引かれて振り込まれるので、ワーカーが振込手数料を負担していることになります。
発生する税金は住民税と所得税

所得を得ると原則として所得税と住民税が課税されます。会社員の場合は毎月会社が計算して給与から天引きされ、納税手続きを行なってくれます。
クラウドソーシングではワーカーとクライアントやクラウドソーシングサービスは雇用契約ではないため、ワーカーが自分で所得を申告して所得税と住民税を納税する必要があります。
所得税の申告
後述する一定以上の収入を得ると確定申告が必要となります。税務署で確定申告を行って所得額を申告すると、所得額に応じて所得税が課税されます。
住民税の申告
住民税は所得が少なくても申告する必要があります。
税務署で確定申告を行った場合は、その内容から所得がわかるので住民税の申告は不要です。
確定申告をしない場合は、1月1日時点でお住まいの市区町村の役所に住民税の申告を行う必要があります。
確定申告は必須?

確定申告が必要なケース
クラウドソーシングで得た収入は所得の種類と金額によって、自分で確定申告を行う必要があります。
なお、クラウドソーシングで得た収入は給与所得ではなく、雑所得か事業所得として扱われます。
雑所得の場合
会社員の方が副業としてクラウドソーシングで収入を得た場合は、この雑所得に該当することが多いでしょう。
雑所得では所得が20万円以上の場合に確定申告が必要です。
事業所得の場合
長期間に渡って本業としてクラウドソーシングで収入を得ている場合は事業所得とみなされます。
事業所得では所得が48万円以上の場合に確定申告が必要です。
雑所得と事業所得の分岐点
雑所得と事業所得の区別は売上の金額で決まらず、事業に該当するかどうかで判断されます。しかし、この「事業に該当するか」という基準も明確な線引きが難しいところです。
会社員として本業の仕事をしている場合でも、個人事業主としてクラウドソーシングで毎日継続して仕事を行っていれば、事業所得としてみなされることもあります。事業所得での申告を検討するのであれば、事業所得に該当するのか税務署に相談してみましょう。
源泉徴収票は交付される?
会社員であれば年末調整を行った後に、源泉徴収票が手元に届くと思います。これは給与を支払った場合に企業は従業員に源泉徴収票を交付する義務があるためです。確定申告にはこの源泉徴収票を提出します。
クラウドソーシングの場合は雇用契約ではないので、源泉徴収票を交付する義務がありません。そのため、クライアントから源泉徴収票が交付されない場合もあります。その場合、ワーカーは自分で支払われた収入を記録して、クライアントの支払い履歴から源泉徴収の状況を把握しておく必要があります。
クラウドソーシングサービスによっては支払いの履歴を報告書の形式で発行してくれる場合もあるので、自分が利用したクラウドソーシングサービスでの対応を確定申告前に確認しておくことをおすすめします。
収入から経費を差し引いて節税する

ここで収入と所得の違いについて簡単に確認しましょう。
収入とはクラウドソーシングなどで得た「売上」のことで、ここから業務に使用した必要経費を差し引いたものが「所得」になります。納税額は「所得」額によって決まります。経費を計上すれば所得が減るので、適切に経費を把握することが節税につながります。
以下、代表的な経費の種類について説明します。
消耗品費
業務に必要なパソコン、カメラ、プリンタなどは10万円未満の場合、「消耗品費」という勘定科目で経費に計上できます。他にはプリンタのインク代やプリント用紙などが消耗品費の対象です。
なお、10万円以上の場合は「減価償却資産」として資産に計上し、耐用年数(パソコンは4年)で割った額を毎年費用として計上します。
消耗品費と減価償却費の判別は使用される単位の価格で行います。パソコンは「1組」で数えるので、本体が7万円のデスクトップパソコンと4万円のディスプレイを購入した場合は、合計10万円以上で減価償却資産となります。
通信費
クラウドソーシングでは主にインターネットを利用するので、インターネットの月額使用料は経費として考えられます。同様に携帯電話やスマートフォンの利用料金も通信費として計上できるでしょう。
ただし、これらは「家事按分」といって仕事で使った割合を算出して、その分だけを経費として計上することになります。全額を経費にできるわけではないので注意してください。
支払手数料
先に述べたクラウドソーシングのシステム手数料と、報酬の振込手数料は「支払手数料」として計上が可能です。
2つを区別するために振込手数料を「雑費」として計上する方法もあります。これは管理としてどちらが正しいというわけではなく、年度の途中などで費目を変更しなければ問題ありません。
旅費交通費
仕事における打ち合わせや取材で必要となった、公共交通料金やタクシー代は「旅費交通費」として計上できます。
自家用車で移動した場合のガソリン代も旅費交通費に該当しますが、計上できるのは仕事で使った分だけです。
まとめ
会社勤めの場合は給与から天引きで済む税金の手続きを、クラウドソーシングでは自身で行う必要があります。
確定申告が必要な要件は雑所得か事業所得かによって分かれますが、どちらも経費を計上することで所得を圧縮することができます。
領収書や入出金履歴の管理に加えて、家事按分や減価償却などの経費を利用して上手に節税しましょう。