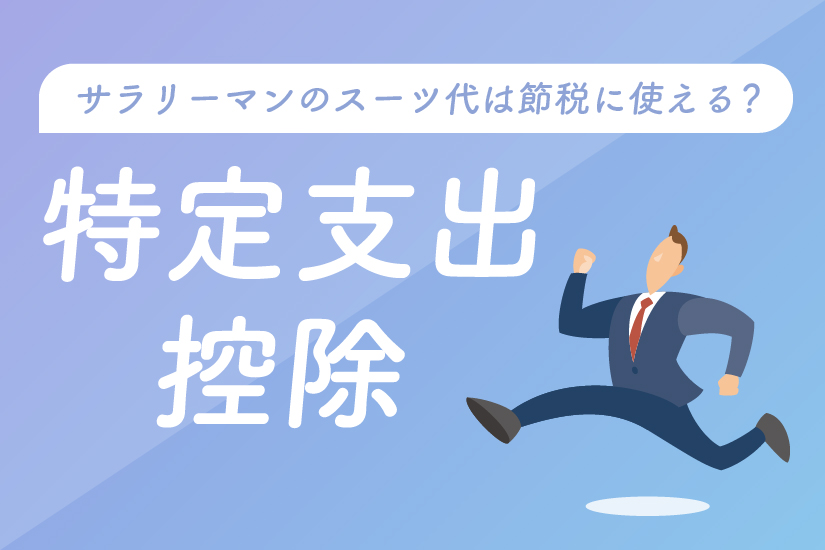サラリーマンにとって、スーツは必需品です。スーツを買い替える時に「スーツ費用も経費で落とせたらいいのに…」と思う人も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、サラリーマンのスーツ費用は経費にならない場合が多いです。ただし、スーツ費用が一定の金額よりも大きくなった場合は、特定支出控除制度によって経費として計上できる場合があります。
この記事では、サラリーマンがスーツ費用や業務に必要なものの費用を経費計上する方法について解説します。
目次
サラリーマンのスーツは経費にならない場合が多い

サラリーマンにとってスーツは仕事上の必需品ですが、経費としては計上できない場合が多くあります。
作業着や制服は経費で購入され会社から支給されることが多くありますが、スーツは基本的に自腹です。これは、スーツはプライベートでも使う可能性があるので、100%仕事のみに使っていることを証明するのが難しいからという理由です。
特定支出控除制度でサラリーマンのスーツ費用を経費にできる

スーツ代は経費にならないことが多いですが、スーツ費用が高額になる場合は、特定支出制度を利用して経費計上し還付金を受けられる可能性があります。
特定支出控除制度とは、スーツ費用をはじめとする特定の支出が給与所得控除額の半分を超えた場合に利用できる制度です。
サラリーマンが利用できる、特定支出控除制度について解説します。
給与所得控除とは
給与所得控除とは、年間の給与に応じて収入から控除され、所得税を計算する制度です。
給与所得控除額について、国税庁のサイトには以下のように掲載されています。
給与等の収入金額:1,625,000円まで
給与所得控除額:550,000円
給与等の収入金額:1,625,001円~ 1,800,000円
給与所得控除額:収入金額×40%-100,000円
給与等の収入金額:1,800,001円~ 3,600,000円
給与所得控除額:収入金額×30%+80,000円
給与等の収入金額:3,600,001円~ 6,600,000円
給与所得控除額:収入金額×20%+440,000円
給与等の収入金額:6,600,001円~8,500,000円
給与所得控除額:収入金額×10%+1,100,000円
給与等の収入金額:8,500,001円以上
給与所得控除額:1,950,000円(上限)
引用:国税庁|No.1410 給与所得控除 ※令和2年分以降の金額
特定支出控除の計算方法
スーツ費用が特定支出控除の対象かどうかを計算する方法について解説します。
年収600万円だった場合の特定支出控除について、以下でシミュレーションしてみました。
年収:600万円
年間のスーツ代:30万円
給与所得控除額の半分:174万円÷2=87万円
給与所得控除額は、会社からもらう源泉徴収票から確認できます。
上記の場合スーツ費用だけ見ると給与所得控除額の半分を超えていないので、特定支出控除を受けることはできません。
スーツ以外で特定支出の対象になるもの

スーツ費用以外で特定支出になるものとしては、主に以下のものがあります。
- 自腹で支払う通勤費や、支給される通勤費を超えた場合
- 単身赴任者が自宅に帰る際の費用
- 業務に関する書籍の購入費用
- 会社の得意先との交際費や接待費
- 資格取得のための費用
- 転勤の際の引越し費用
ただし、上記の項目は、会社から経費や補助を受けられるものもあります。
補助を受けられない場合は領収書をとっておき、給与所得控除額の半分を超えた場合は確定申告をすることで控除が受けられます。
特定支出控除の注意点
特定支出控除を受けるためには、自分で確定申告を行う必要があり、手間がかかります。
また、業務に関する支出は、会社の経費として申請できたり補助を受けられたりすることも多くあります。特定支出の対象となるもののうち、自腹で払っているものやその金額を一度確認するのがおすすめです。
経費計上することで節税効果が期待できるものの、特定支出控除を受けるためには給与所得控除の半分以上の支出をする必要があります。
自己負担額自体が大きくなってしまうので、節税効果よりも出費の方が多くなる可能性もある点に注意が必要です。
まとめ:スーツ費用は基本的には経費にならない
サラリーマンのスーツ費用は、基本的には経費になりません。ただしスーツ費用が給与所得控除額の半分を超えた場合は、特定支出控除制度を利用して経費として計上し、確定申告することで還付金を得られる可能性があります。
スーツをはじめ、業務に必要な支出があった場合は領収書を保管しておき、給与所得控除額の半分を超えた場合は確定申告してみるのも1つの方法です。
ただし、業務に関する支出は会社で経費申請したり補助が出たりすることも多くあり、その場合は特定支出控除の対象とはなりません。
節税ハックでは、サラリーマンの節税対策について記事を掲載しています。ぜひ他の記事もチェックしてみてください。