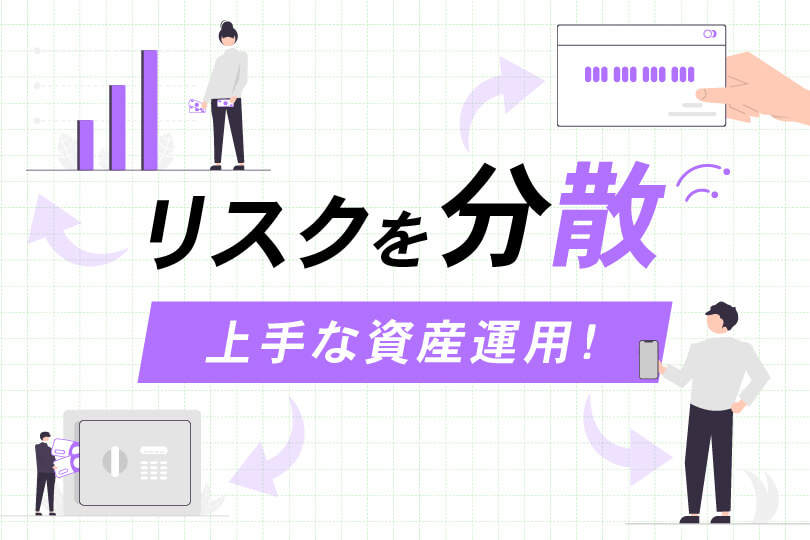今日、新聞やテレビでよく「資産運用」という言葉を耳にするようになりました。
実際、日本証券業協会の調査によると、NISA口座の開設数は年々増加しているようです。
参考)日本証券業協会「NISA口座開設利用状況調査結果2021」
ところで、あなたは資産運用のリスクについてきちんと理解できているでしょうか?
「なんとなく理解しているけれどリスクが怖くて思ったより資産を増やすことができていない」という悩みを抱えていらっしゃる方も多いかもしれません。
この記事では、資産運用する際の「リスク分散」に焦点を当て、リスク分散の重要性や方法について解説していきます。
- リスクを分散させる重要性
- 分散方法の種類
- 分散投資のポイント
目次
リスク=危険ではない

資産運用に関して、「リターン」や「リスク」という言葉をよく聞くと思います。
リスクと聞くと危険や損失というイメージがあるかと思いますが、資産運用を行う際のリスクとは「不確実性」のことです。
投資の結果は正確に予測することができません。そのため、どの程度のリターンがあるか分からないというリターンのブレを「リスク」と呼ぶのです。
つまり、投資にはリスク(危険)があるから手を出さない方がいいというわけではないのです。
投資では、その目的にあったリスクやリターンを選ぶことが大切になります。
自分の大切な資産を長い目で育てていきたいと思ったとき、なるべくならローリスクで運用したいものですよね。そのときに重要となるのが「リスクの分散」なのです。
リスクを分散させる重要性

分散投資の重要性を表す「卵を1つのカゴに盛るな」というイギリスの有名な格言をご存知でしょうか。
持っている全ての卵を1つのカゴに入れていたとします。
そのカゴを落としてしまったら、卵はどうなるでしょうか?
おそらく全ての卵が割れてしまうはずです。
しかし、あらかじめいくつかのカゴに卵を分けて入れておくとどうでしょうか?
1つのカゴを落としてしまっても、残りのカゴに入っている卵は無事です。
つまり投資対象を複数に分けることで、1つの商品が値下がりしてもその他の商品で補うことができ、ひいてはリスクの低減につながるということを表しています。
資産運用を行う上で、リスクについて理解することはとても大切です。
高いリターンを狙って、全資産を投入した株価が急落してしまったら…。
「こうなるなんて思わなかった」「これほどリスクがあると思っていなかった」と言っても、お金は返ってきません。
また証券会社や銀行の担当者に任せているから大丈夫!と思っていらっしゃる方もいると思います。
たしかに、知識の豊富な担当者は頼れる存在です。しかし資産を運用する張本人として、リスクを分散させる重要性を自らも理解したうえで取引するようにしたいものです。
さまざまな分散方法

一言で分散と言っても、さまざまな方法があります。
銘柄分散、資産分散、通貨分散、地域分散、時間分散などが挙げられます。
ここでは、それぞれについて解説していきます。
銘柄分散
特定の資産や投資対象に投資するときに、いくつかの銘柄に分けて投資する方法です。
株式投資の場合をみてみましょう。
例えばA社の株だけを保有していたとします。するとA社の株価が暴落したら大きな損失を負うことになります。
しかし資産をA社とB社の株に分けて保有しておけば、万一A社の株が暴落してしまっても損失の幅は縮小されます。またB社の株が値上がりしていれば、A社の損失を補うことにもなるのです。
セクター分散とは
銘柄分散ではセクターを意識することも大切です。
ここでのセクターとは、食料品や医薬品、銀行、工業など、株式市場の上場企業を「業種ごと」に分けた単位を指します。
セクターはそれぞれ特徴を持っています。
例えば医薬品なら新薬の開発などで大きく株価が変動しやすく、常に一定の需要がある食料品は安定した値動きをすることが多いといえるでしょう。
つまり「食料品と医薬品」「自動車と銀行」など、セクターを意識して分散投資することでさらなるリスクの低減につながるのです。
反対に1つのセクター内の企業だけで銘柄分散をしてしまうと、そのセクター全体の株価が下がったときのリスクが高くなりますので気をつけましょう。
資産分散
同じ資産で複数の銘柄に分散投資する銘柄分散とは異なり、さらに広い視点で分散する方法が資産分散です。
このときの資産とは、預貯金や債券、株式、不動産などを指します。
例えば、これまで預貯金しか持っていなかったけれど株式投資を始めてみたという行為も資産の分散の1つです。
通貨分散・地域分散
まず通貨の分散とは、複数の通貨に分けて投資する方法です。
日本円だけで投資するのではなく、ドルやユーロなど様々な通貨を組み合わせて投資することで為替変動の影響を和らげてくれる効果があります。
また地域の分散とは、国内と海外、先進国と新興国のように異なる国や地域の資産を組み合わせて投資することです。
国が変われば、もちろん経済情勢も社会情勢も変わってきます。さまざまな国や地域の株式や債券へ投資することで、景気の悪化などによるリスクを低減します。
このように、日本だけでなく海外へ目を向けることも大切なリスクの分散となるのです。
時間分散
時間分散とは、株式や債券を購入するタイミングを分ける投資方法です。
一度に全ての資金を投資するのではなく、少しずつ分けて購入することでリスクを減らすことができます。
代表的な時間分散の方法として、ドルコスト平均法が挙げられます。
ドルコスト平均法とは、価格の変動がある有価証券などの商品を一定金額で長期にわたって定期的に購入する方法のことです。
購入金額を一定額に設定するため、商品価格が高いときの購入量は減少し、商品価格が安いときに購入量は増加します。
すると、長い目でみると1回あたりの投資価格は平準化されていき、急な値下がりなどがあっても損失のリスクを抑えることができるのです。
分散投資のポイント「ポートフォリオ」

みなさんは「ポートフォリオ」という言葉を聞いたことがありますか?
ポートフォリオとは、具体的な金融商品の組み合わせのことを指します。
「外国株式30%、日本株式30%、外国債券15%、日本債券25%としたとき、株式は何という銘柄で何株にするか…」などを検討し自分にあった資産を構成していくのです。
ポートフォリオにおける資産構成の割合は人それぞれです。
投資にあてることができる資産の状況、どの程度のリスクを取ることができるのか、どの程度のリターンを見込んでいるのかなど様々な状況に鑑みてください。
それらを考慮したうえで、先ほど説明したさまざまな分散方法を活かし、自分にあったポートフォリオを作成してみましょう。
またポートフォリオは一度作成したら終わりではありません。
リバランス といって、自分が設定した期間や、当初の資産配分から大きく変わってしまったときなどに元の配分に戻すことも大切です。
さらに自分自身のリスクに対する考え方が変化したとき、資産運用の目的が変わったときなどはポートフォリオの構成から改めて見直す必要があるでしょう。
リスクを抑えた資産運用にポートフォリオの作成・見直しは不可欠なのです。
分散投資でも消せないリスク

このようにさまざまな方法で分散投資していても、消し去ることができないリスクもあります。
それはシステマティック・リスクと呼ばれるもので、例えば景気の悪化のような市場全体のリスクのことを指します。
最近では新型コロナウイルスの感染拡大によるマーケット全体の低迷がそれにあたります。残念ながらこのようなリスクを避けることはできません。
反対に分散投資で抑えられるリスクをアンシステマティック・リスクと呼びます。
ポートフォリオなどによるリスク軽減には限界があるので万能ではありません。そのことを知っておけば、パニック状態に陥り保有資産を慌てて処分(売却)する「狼狽売り」の前に冷静になれるのではないでしょうか。
大災害や政変で10年に1度の大暴落が発生しても、長い目で見れば一定の水準に収束していくものです。正しくリスクを分散して資産運用を継続すれば、利益につながる可能性が高いと言えるでしょう。
まとめ
資産運用を行う上で、リスクを分散させる重要性について理解していただけましたでしょうか。
ギャンブルとは異なり、資産運用ではある程度のリスクは自分で低減させることができるのです。
リバランスやポートフォリオの見直しは運用の収益アップにもつながります。
ぜひこの機会に自分のポートフォリオを今一度確認してみてはいかがでしょうか。これまで見落としていたリスクに気がつくかもしれませんよ。